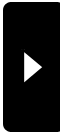スポンサーリンク
第31回 celemony melodyne editer
しかし、暑いです。どうにかならないものでしょうか。
原発停止により、どこにいっても節電、節電です。
まあ、節電も大切ですが、熱中症にならないように、水分補給と塩分補給には十分気をつけましょう。
ちなみに、うちの職場は、もともとエアコンとは縁が薄いので、普段の夏とあまり変わりはありません。
さて、前回の記事でチラッと触れたcelemony社のmelodyne editerについて紹介したいと思います。
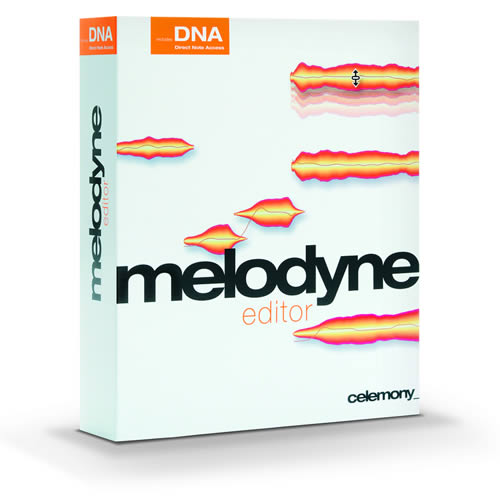
これはコンピュータの音楽製作ソフト上で音程や音の長さを自在にコントロールできるアプリケーションソフトになります。
僕がカセットMTRで遊んでいた15年程前の頃は、MIDIデータであれば、そういったこともできたのですが、オーディオデータでそれをやることは、まさに「神の領域」の技でした。
まあ、音程や音の長さを自在にコントロールといっても、当然、限界があります。
もともとは、ボーカルや楽器の微妙なピッチのズレを修正するのが目的のソフトでるあるため、原音から大幅に音程を変えると、不自然な感じになってしまいます。
melodyneというソフト自体は10年くらい前から存在していて、現在まで何度もバージョンアップを繰り返し、かなりの完成度を誇るソフトになっています。
先ほど述べた不自然さ等もバージョンアップの過程で随分と改善されたようです。
さらに、ボーカルやサックス、トランペット等のモノフォニック(単音)の解析だけではなく、ギターやピアノ等のポリフォニック(和音)の解析も可能になりました。
まだ和音の解析は試したことはないのですが、簡単にいうと、例えばAm(ラ、ド、ミ)のコードを弾かなければならないところで、間違えてA(ラ、ド#、ミ)のコードを弾いてしまった場合に、あとからド#をドに差し替えることができるということです。
まさに「神の領域」の技です。すごい時代になったものです。
インチキといえばインチキだと思いますが、実際、プロの現場でも使われているようです。
このブログでは、BOØWYのBELIEVEのサビのコーラス、WORKING MANのサビの1オクターブ下のコーラス、あとMEMORYの部分的なボーカルピッチ修正で使用しています。
あとは全て本物です(笑)。
活用方法としては、まずメインボーカルのトラックを別トラックにコピーペーストします。
次にそれの音程を変えることでコーラスパートを作ってハモらせます。
でも、出来上がったコーラスですが、オケに混ぜて聴く分にはまだ聴けるのですが、正直、生成したコーラスパートだけで聴いてみると、うーん、何だかなぁ...。って感じです。
人間の声という超アナログなものを加工するわけなので、無理やり手を加えれば、やはりどこか不自然になってしまいます。
もっとも、マニュアルもろくに読まずに使っているので、十分にソフトの性能を引き出せていないという話もあります。
ちゃんと使いこなせれば、かなり自然な感じになるのでしょうね。
まあ、僕の腕の問題は置いておいて、この動画を見ていただければ、メロダイン エディターのスゴさが理解していただけるかと思います。
正直なところ、自分自身は、本当に歌ってナンボ、本当に弾いてナンボという思いが強いため、滅多に使うことはないのですが、好き嫌いは別にして、スゴいソフトであることは間違いがないので興味本位で買ってみました。
3万円弱でこんな夢のような機能が手に入るのならば、まあ、買っても損はないのではないでしょうか。
僕も、もう少し勉強して有効活用しないと元が取れないので頑張ります。
原発停止により、どこにいっても節電、節電です。
まあ、節電も大切ですが、熱中症にならないように、水分補給と塩分補給には十分気をつけましょう。
ちなみに、うちの職場は、もともとエアコンとは縁が薄いので、普段の夏とあまり変わりはありません。
さて、前回の記事でチラッと触れたcelemony社のmelodyne editerについて紹介したいと思います。
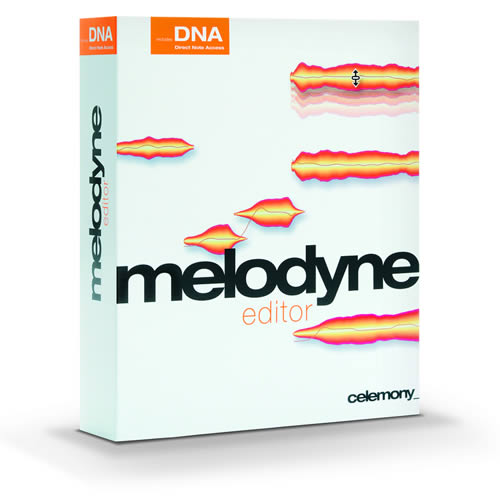
これはコンピュータの音楽製作ソフト上で音程や音の長さを自在にコントロールできるアプリケーションソフトになります。
僕がカセットMTRで遊んでいた15年程前の頃は、MIDIデータであれば、そういったこともできたのですが、オーディオデータでそれをやることは、まさに「神の領域」の技でした。
まあ、音程や音の長さを自在にコントロールといっても、当然、限界があります。
もともとは、ボーカルや楽器の微妙なピッチのズレを修正するのが目的のソフトでるあるため、原音から大幅に音程を変えると、不自然な感じになってしまいます。
melodyneというソフト自体は10年くらい前から存在していて、現在まで何度もバージョンアップを繰り返し、かなりの完成度を誇るソフトになっています。
先ほど述べた不自然さ等もバージョンアップの過程で随分と改善されたようです。
さらに、ボーカルやサックス、トランペット等のモノフォニック(単音)の解析だけではなく、ギターやピアノ等のポリフォニック(和音)の解析も可能になりました。
まだ和音の解析は試したことはないのですが、簡単にいうと、例えばAm(ラ、ド、ミ)のコードを弾かなければならないところで、間違えてA(ラ、ド#、ミ)のコードを弾いてしまった場合に、あとからド#をドに差し替えることができるということです。
まさに「神の領域」の技です。すごい時代になったものです。
インチキといえばインチキだと思いますが、実際、プロの現場でも使われているようです。
このブログでは、BOØWYのBELIEVEのサビのコーラス、WORKING MANのサビの1オクターブ下のコーラス、あとMEMORYの部分的なボーカルピッチ修正で使用しています。
あとは全て本物です(笑)。
活用方法としては、まずメインボーカルのトラックを別トラックにコピーペーストします。
次にそれの音程を変えることでコーラスパートを作ってハモらせます。
でも、出来上がったコーラスですが、オケに混ぜて聴く分にはまだ聴けるのですが、正直、生成したコーラスパートだけで聴いてみると、うーん、何だかなぁ...。って感じです。
人間の声という超アナログなものを加工するわけなので、無理やり手を加えれば、やはりどこか不自然になってしまいます。
もっとも、マニュアルもろくに読まずに使っているので、十分にソフトの性能を引き出せていないという話もあります。
ちゃんと使いこなせれば、かなり自然な感じになるのでしょうね。
まあ、僕の腕の問題は置いておいて、この動画を見ていただければ、メロダイン エディターのスゴさが理解していただけるかと思います。
正直なところ、自分自身は、本当に歌ってナンボ、本当に弾いてナンボという思いが強いため、滅多に使うことはないのですが、好き嫌いは別にして、スゴいソフトであることは間違いがないので興味本位で買ってみました。
3万円弱でこんな夢のような機能が手に入るのならば、まあ、買っても損はないのではないでしょうか。
僕も、もう少し勉強して有効活用しないと元が取れないので頑張ります。
Posted by cha-key at
◆2011年07月03日20:40
│機材公開
第29回 Hughes&Kettner ZenTera ②
前回の機材紹介に引き続き、Hughes&Kettner(ヒューズアンドケトナー)のモデリングギターアンプZenTera(ゼンテラ)について書きたいと思います。

アンプの基本的な部分については前回紹介したとおりですが、このアンプには、エフェクターも搭載されており、ZenTeraだけで音作りが完結できるようなシステムになっています。
エフェクトそのものは、それほど奇抜なものはなく、ワウ、オートワウ、コンプ、チューブスクリーマー、ファズ、ミッドブースター、空間系としてコーラス、フランジャー、フェーザー、ディレイ、リバーブといったオーソドックスなものばかりですが、さすがにエフェクトのクオリティは高く、どれも使えるものになっています。
エフェクトの操作性ですが、各エフェクトのパラメータは2つしかありません。
ファズで言えばゲインとレベルの2つだけ。
ディレイでいえばディレイタイムとフィードバックの2つだけ。
コーラスでいえばモジュレーションの速さと深さの2つだけ。
あとは原音とエフェクト音とのミックスバランスレベルが調整できますが、操作できるのはそれだけです。
前に所有していたT.C.electronicのG-SYSTEMなんかは1つのエフェクトごとに10くらいパラメータがありました。
エフェクトの質そのものは文句の付けようがないものでしたが、正直かまえるところが多すぎるため、途中で訳が分からなくなって、「まあ、こんな感じでいいや」となるパターンもありました。
ZenTeraのこのシステムは必要最小限のパラメータであるため、訳が分からなくなることは絶対に有りません(笑)。
パラメータ2つはアンプのコントロールセクションの隣にある2つのツマミで操作します。
ツマミで操作できるので、コンパクトエフェクターと同じ感覚で操作ができます。
操作が分かりやすいっていうのは大きなポイントだと思います。
プログラムパッチは128種類用意されており、1番~100番までが書き換え可能で、101番~128番まではデフォルトプログラムで書き換え不能となっています。(1番~28番と全く同じプログラムパッチになっています。)
普通に使用する分には20種類もあれば十分なのではないでしょうか。
専用フットコントローラーであるZ-BOARDですが、前にも触れましたが、たかがフットコントローラーなのに定価73,500円もします。

確かに値段に見合うだけの頑丈そうな作りはしています。
2つ搭載されているペダルなんかは、どっかの工場に置いてある機械のようなルックスです。
2つのペダルはそれぞれボリュームペダルとワウペダルになっていますが、ワウペダルについては、別の機能をアサインすることが可能です。
例えばアンプのゲインをアサインすると、ペダル操作でアンプのゲインをコントロールできたり、ディレイタイムをアサインしておけば、リアルタイムでディレイタイムをコントロールすることができます。
アイディア次第で面白いことができそうです。
また、他のアンプにあまりない機能としてS/P DIFによるデジタルアウトプットを装備していることが挙げられます。
これにより24Bit、44.1kHzのデジタル信号で音を出すことができます。
理論上、信号を劣化させることなく外部ミキサーやレコーダーに送ることができます。
大規模な会場等でシールドを引き回さなければならない場合には役に立ちそうです。
実はこのアンプを入手してから色々調べて知ったのですが、布袋さんの2003年リリースのアルバムDOBERMANは、このZenTeraを使用して製作されたそうで、ツアーの際は、デジタルアウトで直接、卓に送り、レコーディング時と同じ(CDと同じ)サウンドをライブで再現していたそうです。
うちの環境では、アンプからデジタルでオーディオインターフェース(コンピュータに接続して録音する機器)に送っていますが、アンプとオーディオインターフェースとの距離は50cm程しか離れていないため、デジタルでもアナログでも聴感上違いが分かりません(笑)。
(まあ、デジタルってだけで劇的に変わってしまったら、うちのアナログ環境って一体どうなのよって話になって逆に困るんですが)
せっかくある機能なので使わなきゃもったいないという理由だけでデジタルアウトで録音しています(爆)。
メリットといえばステレオアウトなのにケーブルが1本で済むことでしょうか。
まあ,多少なりとも音質改善につながっていると思いたいところです。
ちなみにBOØWYのMORALをデジタルアウトで録音しました。
曲こそ違いますが、ハイウェイに乗る前にとアンプのセッティングそのものは全く一緒なので聞き比べてみると面白いかもしれません。
あと、細かい部分で、アンプのプログラムのメモリー記憶用の内蔵の電池について触れておきます。
こういった機器を中古で買うと、いつ電池が切れるんだろうと心配になりますが、ZenTeraは充電式のバッテリーを搭載しているため、こまめにアンプに電源を入れて使ってやれば、電池の交換は必要ありません。
電池交換のためだけにメーカーに高い送料を払って交換してもらったり、自己責任で分解して電池交換しなくても済むのはありがたい話です。
以上、2回にわたって、ZenTeraの紹介をしてきましたが、自分自身まだまだ使い切れていないので、今後、じっくりと研究したいと思います。
アンプの基本的な部分については前回紹介したとおりですが、このアンプには、エフェクターも搭載されており、ZenTeraだけで音作りが完結できるようなシステムになっています。
エフェクトそのものは、それほど奇抜なものはなく、ワウ、オートワウ、コンプ、チューブスクリーマー、ファズ、ミッドブースター、空間系としてコーラス、フランジャー、フェーザー、ディレイ、リバーブといったオーソドックスなものばかりですが、さすがにエフェクトのクオリティは高く、どれも使えるものになっています。
エフェクトの操作性ですが、各エフェクトのパラメータは2つしかありません。
ファズで言えばゲインとレベルの2つだけ。
ディレイでいえばディレイタイムとフィードバックの2つだけ。
コーラスでいえばモジュレーションの速さと深さの2つだけ。
あとは原音とエフェクト音とのミックスバランスレベルが調整できますが、操作できるのはそれだけです。
前に所有していたT.C.electronicのG-SYSTEMなんかは1つのエフェクトごとに10くらいパラメータがありました。
エフェクトの質そのものは文句の付けようがないものでしたが、正直かまえるところが多すぎるため、途中で訳が分からなくなって、「まあ、こんな感じでいいや」となるパターンもありました。
ZenTeraのこのシステムは必要最小限のパラメータであるため、訳が分からなくなることは絶対に有りません(笑)。
パラメータ2つはアンプのコントロールセクションの隣にある2つのツマミで操作します。
ツマミで操作できるので、コンパクトエフェクターと同じ感覚で操作ができます。
操作が分かりやすいっていうのは大きなポイントだと思います。
プログラムパッチは128種類用意されており、1番~100番までが書き換え可能で、101番~128番まではデフォルトプログラムで書き換え不能となっています。(1番~28番と全く同じプログラムパッチになっています。)
普通に使用する分には20種類もあれば十分なのではないでしょうか。
専用フットコントローラーであるZ-BOARDですが、前にも触れましたが、たかがフットコントローラーなのに定価73,500円もします。

確かに値段に見合うだけの頑丈そうな作りはしています。
2つ搭載されているペダルなんかは、どっかの工場に置いてある機械のようなルックスです。
2つのペダルはそれぞれボリュームペダルとワウペダルになっていますが、ワウペダルについては、別の機能をアサインすることが可能です。
例えばアンプのゲインをアサインすると、ペダル操作でアンプのゲインをコントロールできたり、ディレイタイムをアサインしておけば、リアルタイムでディレイタイムをコントロールすることができます。
アイディア次第で面白いことができそうです。
また、他のアンプにあまりない機能としてS/P DIFによるデジタルアウトプットを装備していることが挙げられます。
これにより24Bit、44.1kHzのデジタル信号で音を出すことができます。
理論上、信号を劣化させることなく外部ミキサーやレコーダーに送ることができます。
大規模な会場等でシールドを引き回さなければならない場合には役に立ちそうです。
実はこのアンプを入手してから色々調べて知ったのですが、布袋さんの2003年リリースのアルバムDOBERMANは、このZenTeraを使用して製作されたそうで、ツアーの際は、デジタルアウトで直接、卓に送り、レコーディング時と同じ(CDと同じ)サウンドをライブで再現していたそうです。
うちの環境では、アンプからデジタルでオーディオインターフェース(コンピュータに接続して録音する機器)に送っていますが、アンプとオーディオインターフェースとの距離は50cm程しか離れていないため、デジタルでもアナログでも聴感上違いが分かりません(笑)。
(まあ、デジタルってだけで劇的に変わってしまったら、うちのアナログ環境って一体どうなのよって話になって逆に困るんですが)
せっかくある機能なので使わなきゃもったいないという理由だけでデジタルアウトで録音しています(爆)。
メリットといえばステレオアウトなのにケーブルが1本で済むことでしょうか。
まあ,多少なりとも音質改善につながっていると思いたいところです。
ちなみにBOØWYのMORALをデジタルアウトで録音しました。
曲こそ違いますが、ハイウェイに乗る前にとアンプのセッティングそのものは全く一緒なので聞き比べてみると面白いかもしれません。
あと、細かい部分で、アンプのプログラムのメモリー記憶用の内蔵の電池について触れておきます。
こういった機器を中古で買うと、いつ電池が切れるんだろうと心配になりますが、ZenTeraは充電式のバッテリーを搭載しているため、こまめにアンプに電源を入れて使ってやれば、電池の交換は必要ありません。
電池交換のためだけにメーカーに高い送料を払って交換してもらったり、自己責任で分解して電池交換しなくても済むのはありがたい話です。
以上、2回にわたって、ZenTeraの紹介をしてきましたが、自分自身まだまだ使い切れていないので、今後、じっくりと研究したいと思います。
Posted by cha-key at
◆2011年05月15日00:00
│機材公開
第27回 Hughes&Kettner ZenTera ①
さて、前回、少し触れましたが機材環境を一新しました。
新しく入手したアンプについて紹介したいと思います。
10年ほど前に発売されたものなのですが、Hughes & Kettner(ヒューズ & ケトナー)のZenTera(ゼンテラ)というアンプです。

はいはい。分かってます。
またモデリングアンプかよ!って声が誰かさんから聞こえてきそうですが、別にいいでしょ、好きなんだから。
まあ細かい使用感は後で述べることにします。
とにかく10年ほど前に流行したモデリングアンプのブームの中で頂点にあったのが、おそらく、このZenTeraだったのではないかと思います。
当時、価格からして税込み本体価格535,500円 っていうのは、アマチュアには簡単に手が出せない高嶺の花でした。
っていうのは、アマチュアには簡単に手が出せない高嶺の花でした。
付属品のフットスイッチボードだけでも73,500円って、それだけで上等なコンパクトエフェクターがいくつか買えてしまいます。
当然、当時は自分が使えるような代物ではないと思っていましたが、10年近く経ち、モデリングアンプのブームも過ぎ去り、最近は値段も落ち着いてきたところに
オークションに納得できる値段で出品されていたため、思わずポチッとやってしまいました。
さすがに値段が値段だけあって、外装のクオリティも高く、黒光りしているボディは強烈な存在感を放っています。

さて、アンプの仕様について簡単に触れたいと思います。
100W×2というステレオ仕様のアンプになります。完全にプロのステージ使用の目的としたアンプです。
家なんかで普通に鳴らそうものなら、いくら田舎といえども間違いなく近所から苦情の電話の嵐となります。
ただYAMAHAのDG100同様に独立したマスターボリュームにより、サウンドクオリティを保ったまま全体音量をコントロールできるため小音量でも満足できる音が得られます。
また、ステレオのラインアウトにはHughes&KettnerのキャビネットシミュレータRED BOX同等の回路が搭載されているため、アンプそのものを鳴らさなくても、迫力のある音を得ることができます。
この機能がないと深夜の作業ができないので個人的には必須の機能です。
マニュアルには、このアンプのウリはダイナミック・セクター・モデリングというテクノロジーにあると書いてあります。
難しいことはよくわかりませんが、元になるアンプの回路をセクションごとに細かく分析し、それらのダイナミックな相互作用をモデル化することのようです。
そして、それを可能にしたのが、24BitのA/Dコンバーターによる116dBのダイナミックレンジと2機の32Bit浮動小数点演算DSPによるレイテンシーの排除にあるとあります。
ますます訳がわからなくなりますが、当時の最新鋭のテクノロジーを集結させ、チューブアンプの歴代の銘器の数々の音に極限まで迫ったということだと思います。
一応、今までにYAMAHAのDG、LINE6の最高峰VETTA2、そしてZenTeraと所有し、実際に弾いてきて、モデリングアンプについては、少しは語れるつもりでいますが、ZenTeraのギターのボリューム変化やピッキングの強弱に対してのトーンへのレスポンスのよさはピカイチだと思います。
VETTAについては3年ほど前に2ヶ月ほどしか所有していなかったので、あまり細かく語れないため、YAMAHAのDGと比較しての話になりますが、ピッキングのダイナミクスについては弱めに弾けばクリーントーンで、強めに弾けばクランチトーンになるという変化はDGよりかなりスムーズというか表現力があるというか自然な感じだと思います。
あと、アンプタイプのバリエーションについては非常に豊富です。フェンダー系、VOX、マーシャルのPLEXIからモダン、ソルダーノ、ブギー、ローランドのJCまでカバーしているため、極上クリーンから激歪みまで1台でこなします。
DGもリード、ドライブ、クランチ、クリーンが用意されてはいるものの、元となる2種類の基本的なサウンドキャラクターが決まっていたので、バリエーションという意味ではそんなに幅広くはありませんでした。まあ、DGはDGで捨てがたい音を出していましたが。(できれば手元に置いておきたかった)
僕のうんちくを聞いたところで訳が分からないと思うので、とりあえず、この動画見ていただければ、大体の感じは掴めると思います。
今のところ、このブログの歌でZenTeraで録ったのはスピッツのロビンソンとBOØWYのハイウェイに乗る前にになります。
ロビンソンはFenderのBlackFaceタイプを使用、ハイウェイはRolandのJC120タイプにZenTera内蔵の歪み系のエフェクトをかまして録りました。
また、ZenTeraは内蔵エフェクトも備えています。
基本的なものが多いのですが、ポイントをおさえたエフェクト群となっています。
このあたりは、また次回にお伝えしたいと思います。
では、とりあえず今回はこのへんで。
新しく入手したアンプについて紹介したいと思います。
10年ほど前に発売されたものなのですが、Hughes & Kettner(ヒューズ & ケトナー)のZenTera(ゼンテラ)というアンプです。
はいはい。分かってます。
またモデリングアンプかよ!って声が誰かさんから聞こえてきそうですが、別にいいでしょ、好きなんだから。
まあ細かい使用感は後で述べることにします。
とにかく10年ほど前に流行したモデリングアンプのブームの中で頂点にあったのが、おそらく、このZenTeraだったのではないかと思います。
当時、価格からして税込み本体価格535,500円
 っていうのは、アマチュアには簡単に手が出せない高嶺の花でした。
っていうのは、アマチュアには簡単に手が出せない高嶺の花でした。付属品のフットスイッチボードだけでも73,500円って、それだけで上等なコンパクトエフェクターがいくつか買えてしまいます。
当然、当時は自分が使えるような代物ではないと思っていましたが、10年近く経ち、モデリングアンプのブームも過ぎ去り、最近は値段も落ち着いてきたところに
オークションに納得できる値段で出品されていたため、思わずポチッとやってしまいました。
さすがに値段が値段だけあって、外装のクオリティも高く、黒光りしているボディは強烈な存在感を放っています。

さて、アンプの仕様について簡単に触れたいと思います。
100W×2というステレオ仕様のアンプになります。完全にプロのステージ使用の目的としたアンプです。
家なんかで普通に鳴らそうものなら、いくら田舎といえども間違いなく近所から苦情の電話の嵐となります。
ただYAMAHAのDG100同様に独立したマスターボリュームにより、サウンドクオリティを保ったまま全体音量をコントロールできるため小音量でも満足できる音が得られます。
また、ステレオのラインアウトにはHughes&KettnerのキャビネットシミュレータRED BOX同等の回路が搭載されているため、アンプそのものを鳴らさなくても、迫力のある音を得ることができます。
この機能がないと深夜の作業ができないので個人的には必須の機能です。
マニュアルには、このアンプのウリはダイナミック・セクター・モデリングというテクノロジーにあると書いてあります。
難しいことはよくわかりませんが、元になるアンプの回路をセクションごとに細かく分析し、それらのダイナミックな相互作用をモデル化することのようです。
そして、それを可能にしたのが、24BitのA/Dコンバーターによる116dBのダイナミックレンジと2機の32Bit浮動小数点演算DSPによるレイテンシーの排除にあるとあります。
ますます訳がわからなくなりますが、当時の最新鋭のテクノロジーを集結させ、チューブアンプの歴代の銘器の数々の音に極限まで迫ったということだと思います。
一応、今までにYAMAHAのDG、LINE6の最高峰VETTA2、そしてZenTeraと所有し、実際に弾いてきて、モデリングアンプについては、少しは語れるつもりでいますが、ZenTeraのギターのボリューム変化やピッキングの強弱に対してのトーンへのレスポンスのよさはピカイチだと思います。
VETTAについては3年ほど前に2ヶ月ほどしか所有していなかったので、あまり細かく語れないため、YAMAHAのDGと比較しての話になりますが、ピッキングのダイナミクスについては弱めに弾けばクリーントーンで、強めに弾けばクランチトーンになるという変化はDGよりかなりスムーズというか表現力があるというか自然な感じだと思います。
あと、アンプタイプのバリエーションについては非常に豊富です。フェンダー系、VOX、マーシャルのPLEXIからモダン、ソルダーノ、ブギー、ローランドのJCまでカバーしているため、極上クリーンから激歪みまで1台でこなします。
DGもリード、ドライブ、クランチ、クリーンが用意されてはいるものの、元となる2種類の基本的なサウンドキャラクターが決まっていたので、バリエーションという意味ではそんなに幅広くはありませんでした。まあ、DGはDGで捨てがたい音を出していましたが。(できれば手元に置いておきたかった)
僕のうんちくを聞いたところで訳が分からないと思うので、とりあえず、この動画見ていただければ、大体の感じは掴めると思います。
今のところ、このブログの歌でZenTeraで録ったのはスピッツのロビンソンとBOØWYのハイウェイに乗る前にになります。
ロビンソンはFenderのBlackFaceタイプを使用、ハイウェイはRolandのJC120タイプにZenTera内蔵の歪み系のエフェクトをかまして録りました。
また、ZenTeraは内蔵エフェクトも備えています。
基本的なものが多いのですが、ポイントをおさえたエフェクト群となっています。
このあたりは、また次回にお伝えしたいと思います。
では、とりあえず今回はこのへんで。
Posted by cha-key at
◆2011年04月15日00:00
│機材公開
第25回 YAMAHA Pacifica Custom
東北関東大震災が起ってから既に十日余が経ちました。
未だに被害の全容が掴めず、日に日に増え続ける犠牲者の数に胸が締め付けられる思いです。
今の自分にできることといえば、募金に協力すること、買い溜めをしないこと、そして祈ることでしょうか。
原発問題も心配です。作業関係者の方の必死の努力でよい方向に向かいつつあるようですが、まだまだ安心できない状況です。
作業終了後のハイパーレスキューの方の会見での家族とのやり取りのエピソードを聞いていたら泣けてきました。
自分を犠牲にして皆を守ろうとする行動は本当に凄いことだと思います。
やれと言われてもやれるものではありません。仮に機器を取り扱える技術があったとしても正直僕にはできません。
本当に凄い人たちです。
これを機に反原発の動きが活発になってくると思いますが、現状として電力供給の約25%を原子力発電に依存しているのだから代替策を考えると難しい問題ですね。
こんな時に個人の趣味について語るブログの更新のしてもいいのだろうかと悩みましたが、被災した方々への思いさえしっかりともっていれば、必要以上に自粛する必要はないと判断し更新することにしました。
機材紹介の記事に関してはひだっち以外の外部からのアクセスも多く、まだまだ先の話かもしれませんが、もしかしたら被災地に住んでいる人が、生活が落ち着いてきたら見てくれるかもしれない。
そんな一瞬のつながりも期待しつつ更新することにします。
ということで機材紹介第8弾です。
周辺機器ばかり紹介していて、肝心なギターについて全然触れていなかったので今回少し触れたいと思います。

現在メインで使用しているギターですが、YAMAHAのPacifica Custom(パシフィカ カスタム)といいます。
消費税が3%から5%になる直前に購入したので、もうかれこれ15年近く使用していることになります。
YAMAHAのPacificaシリーズは色々出ていますが、そのフラッグシップモデルになります。
当時定価250,000円だったと思いますが、確か新品で200,000円位で購入した記憶があります。(途中から定価300,000円に値上がりしたような気がします。)
残念ながら7、8年前にディスコンとなってしまいましたが、希少なためか、探している人が多いのか、現在でも中古市場では高値で取引されているようです。
だからといって今のところ売りに出すつもりはありませんが。
しかし、値段だけでみれば、フェンダーのストラトキャスターやギブソンのレスポールも十分狙えるはずなのに、なぜこのギターを買ったのか?
正直、自分でも全く覚えていません。
10代後半に愛読していたヤングギターの裏表紙にいつもトラ目バリバリのルックスのこのギターが載っており、憧れがあったのは確かです。
無意識のうちに「このギターほしい」と刷り込まれていたのでしょうか?

当時コレを使用していた有名ギタリストはスティーヴィーサラスくらい。
特にサラスのことを好きだったわけではありません。というか当時はサラスを聴いたことすらありませんでした。
何か否定的な話になってきましたが、このギター好きですよ。でなければ、長年メインで使いませんから。
ギターとしての性能は申し分ないと思います。
ボディとネックはWarmoth製、ピックアップはDiMarzio、ピックアップセレクターは5ポジションでミックスポジションはフェイズアウト になります。トレモロユニットはYAMAHA Rockin' Magic-Pro III というフロイドローズライセンスのものです。フロイドローズタイプなのに弦のエンドボールピンを切らなくてもよいのはうれしい仕様です。
最近はほとんど使いませんが、24フレット仕様というのもアドリブをとる際に重宝します。気分が高揚してくるとついつい高い音の方へ行ってしまいがちなので。
ネックも薄めで弾きやすいと思います。
ジャンル的にはロック、ハードロック系向けギターということになると思います。
これでブルースっていうのはチョット...。
音色はアンプやエフェクトでどうにかするとしても、このルックスは何ともならん。
正直なところ、比較できるほど多くのギターを弾いているわけじゃないし、手に馴染んでいるからというだけかもしれませんが、現段階では自分にとってコレが一番しっくりくるギターですね。
未だに被害の全容が掴めず、日に日に増え続ける犠牲者の数に胸が締め付けられる思いです。
今の自分にできることといえば、募金に協力すること、買い溜めをしないこと、そして祈ることでしょうか。
原発問題も心配です。作業関係者の方の必死の努力でよい方向に向かいつつあるようですが、まだまだ安心できない状況です。
作業終了後のハイパーレスキューの方の会見での家族とのやり取りのエピソードを聞いていたら泣けてきました。
自分を犠牲にして皆を守ろうとする行動は本当に凄いことだと思います。
やれと言われてもやれるものではありません。仮に機器を取り扱える技術があったとしても正直僕にはできません。
本当に凄い人たちです。
これを機に反原発の動きが活発になってくると思いますが、現状として電力供給の約25%を原子力発電に依存しているのだから代替策を考えると難しい問題ですね。
こんな時に個人の趣味について語るブログの更新のしてもいいのだろうかと悩みましたが、被災した方々への思いさえしっかりともっていれば、必要以上に自粛する必要はないと判断し更新することにしました。
機材紹介の記事に関してはひだっち以外の外部からのアクセスも多く、まだまだ先の話かもしれませんが、もしかしたら被災地に住んでいる人が、生活が落ち着いてきたら見てくれるかもしれない。
そんな一瞬のつながりも期待しつつ更新することにします。
ということで機材紹介第8弾です。
周辺機器ばかり紹介していて、肝心なギターについて全然触れていなかったので今回少し触れたいと思います。
現在メインで使用しているギターですが、YAMAHAのPacifica Custom(パシフィカ カスタム)といいます。
消費税が3%から5%になる直前に購入したので、もうかれこれ15年近く使用していることになります。
YAMAHAのPacificaシリーズは色々出ていますが、そのフラッグシップモデルになります。
当時定価250,000円だったと思いますが、確か新品で200,000円位で購入した記憶があります。(途中から定価300,000円に値上がりしたような気がします。)
残念ながら7、8年前にディスコンとなってしまいましたが、希少なためか、探している人が多いのか、現在でも中古市場では高値で取引されているようです。
だからといって今のところ売りに出すつもりはありませんが。
しかし、値段だけでみれば、フェンダーのストラトキャスターやギブソンのレスポールも十分狙えるはずなのに、なぜこのギターを買ったのか?
正直、自分でも全く覚えていません。
10代後半に愛読していたヤングギターの裏表紙にいつもトラ目バリバリのルックスのこのギターが載っており、憧れがあったのは確かです。
無意識のうちに「このギターほしい」と刷り込まれていたのでしょうか?

当時コレを使用していた有名ギタリストはスティーヴィーサラスくらい。
特にサラスのことを好きだったわけではありません。というか当時はサラスを聴いたことすらありませんでした。
何か否定的な話になってきましたが、このギター好きですよ。でなければ、長年メインで使いませんから。
ギターとしての性能は申し分ないと思います。
ボディとネックはWarmoth製、ピックアップはDiMarzio、ピックアップセレクターは5ポジションでミックスポジションはフェイズアウト になります。トレモロユニットはYAMAHA Rockin' Magic-Pro III というフロイドローズライセンスのものです。フロイドローズタイプなのに弦のエンドボールピンを切らなくてもよいのはうれしい仕様です。
最近はほとんど使いませんが、24フレット仕様というのもアドリブをとる際に重宝します。気分が高揚してくるとついつい高い音の方へ行ってしまいがちなので。
ネックも薄めで弾きやすいと思います。
ジャンル的にはロック、ハードロック系向けギターということになると思います。
これでブルースっていうのはチョット...。
音色はアンプやエフェクトでどうにかするとしても、このルックスは何ともならん。
正直なところ、比較できるほど多くのギターを弾いているわけじゃないし、手に馴染んでいるからというだけかもしれませんが、現段階では自分にとってコレが一番しっくりくるギターですね。
Posted by cha-key at
◆2011年03月22日00:23
│機材公開
第23回 MORPHEUS DROPTUNE DT1
日に日に暖かくなり、季節は春に向かっていますね。
ちょっと家のことでいろいろあり更新が滞りました。
さて、機材紹介第7弾です。今回もエフェクターです。
今回は、機材の説明をする前に、前置きとして、ギターのチューニングについて話をします。
ご存知のとおりギターという楽器は弦を巻き上げ、弦の張力によって各弦の音高が決まります。
いわゆるギターのノーマルチューニングというのは、6弦(太い弦)から1弦(細い弦)に向かって、E,A,D,G,B,Eとなっています。
でも、世の中の楽曲をみると、必ずしもノーマルチューニングの曲ばかりではありません。
特にハードロックやヘヴィメタルでは、サウンドにヘヴィさを求めるため、ギターのチューニングを全体的に半音、1音低くして音に迫力を出す傾向があります。
チューニングを低くすることで、得られるカッコよさは確かにあります。
ヘビメタ命ということで半音下げの曲だけをずっと弾いていれば何ら問題ないのですが、やっぱり普段から色々な曲を弾きたいわけで、そんな時、いちいちチューニングをし直すのって、結構面倒くさいんですよ。
これが、ロック式トレモロ搭載のギターだと、その面倒くささは、結構どころか、本当に嫌になるくらいの面倒くささになります。(こんなこと書いたってギター弾く人にしか伝わらないと思いますが)
面倒ならギターを2本用意すれば済むことですが、残念なことにウチにはギターは1本しか置いてありません。

そんな面倒くささを解消するために、導入したのが今回紹介する機材MORPHEUS(モーフィアス)のDROPTUNE(ドロップチューン)DT1です。
コレを使うと、チューニングし直すことなく、音高だけ低くすることができます。
ペダルを踏み込むたびに半音、1音、1音半、2音、2音半、3音と半音ステップで音高が低くなります。
あと、オクターブ下げと、それを応用したオクターバーの機能も付いています。
本当にそれぞれの弦がちゃんと正確に半音づつ低くなるの?と疑問を抱きたくなると思いますが、これが意外と正確なんですよ。
まあ、製品の性格上、正確じゃなかったらこのエフェクターの存在意義がなくなってしまいますが...。
前に紹介したBOSSのアコースティックシミュレーターと同様で悪く言ってしまえばインチキですね。
でも、本当に便利です。
実際にレコーディングをする時は、ちゃんとチューニングをしてやり、普段の練習はDROPTUNEで済ますというスタンスがいいのではないでしょうか?
といいつつも、ここのブログのビートルズのイエスタデイは、DROPTUNEを使ってレコーディングしました。
しかし、ビートルズが1音下げチューニングの曲をやっていることも意外です。
まあ、この曲の場合は別にヘヴィさを求めたわけではなく、ベストなキーや奏法的な効率を考えて1音下げにしたんだと思いますが。
ということで、ここのブログのイエスタデイは、BOSSのAC-3とDROPTUNEという虚飾で塗り固められた曲(笑)なのですが、そういったことを伏せて聴いた時にどれだけの人が、そのことに気が付くのか興味深いところです。
ちょっと話はズレますが、よくテレビのヴァラエティ番組で3、4万円のヴァイオリンと億単位の価値があるストラディヴァリウスの音をブラインドテストで聴き当てるとかっていう企画をやると、そこそこ知識をもった人でも、こっちの方がいい音とかいって安物のヴァイオリンを選ぶことがありますが、人の判断基準なんて結構いい加減というか感覚的ですよね。
ブランドに弱かったり、偏見でモノをみたり、高いものがいいものという理論にとらわれて、本質を見抜けない人は意外と多いですね。まあ、僕のことですけど。
このブログは今のところノーマルチューニングの曲が大半なので、DROPTUNEも当分の間は出番はないと思いますが、今後ハードロック等やる場合に登場するかもしれません。
ちょっと家のことでいろいろあり更新が滞りました。
さて、機材紹介第7弾です。今回もエフェクターです。
今回は、機材の説明をする前に、前置きとして、ギターのチューニングについて話をします。
ご存知のとおりギターという楽器は弦を巻き上げ、弦の張力によって各弦の音高が決まります。
いわゆるギターのノーマルチューニングというのは、6弦(太い弦)から1弦(細い弦)に向かって、E,A,D,G,B,Eとなっています。
でも、世の中の楽曲をみると、必ずしもノーマルチューニングの曲ばかりではありません。
特にハードロックやヘヴィメタルでは、サウンドにヘヴィさを求めるため、ギターのチューニングを全体的に半音、1音低くして音に迫力を出す傾向があります。
チューニングを低くすることで、得られるカッコよさは確かにあります。
ヘビメタ命ということで半音下げの曲だけをずっと弾いていれば何ら問題ないのですが、やっぱり普段から色々な曲を弾きたいわけで、そんな時、いちいちチューニングをし直すのって、結構面倒くさいんですよ。
これが、ロック式トレモロ搭載のギターだと、その面倒くささは、結構どころか、本当に嫌になるくらいの面倒くささになります。(こんなこと書いたってギター弾く人にしか伝わらないと思いますが)
面倒ならギターを2本用意すれば済むことですが、残念なことにウチにはギターは1本しか置いてありません。
そんな面倒くささを解消するために、導入したのが今回紹介する機材MORPHEUS(モーフィアス)のDROPTUNE(ドロップチューン)DT1です。
コレを使うと、チューニングし直すことなく、音高だけ低くすることができます。
ペダルを踏み込むたびに半音、1音、1音半、2音、2音半、3音と半音ステップで音高が低くなります。
あと、オクターブ下げと、それを応用したオクターバーの機能も付いています。
本当にそれぞれの弦がちゃんと正確に半音づつ低くなるの?と疑問を抱きたくなると思いますが、これが意外と正確なんですよ。
まあ、製品の性格上、正確じゃなかったらこのエフェクターの存在意義がなくなってしまいますが...。
前に紹介したBOSSのアコースティックシミュレーターと同様で悪く言ってしまえばインチキですね。
でも、本当に便利です。
実際にレコーディングをする時は、ちゃんとチューニングをしてやり、普段の練習はDROPTUNEで済ますというスタンスがいいのではないでしょうか?
といいつつも、ここのブログのビートルズのイエスタデイは、DROPTUNEを使ってレコーディングしました。
しかし、ビートルズが1音下げチューニングの曲をやっていることも意外です。
まあ、この曲の場合は別にヘヴィさを求めたわけではなく、ベストなキーや奏法的な効率を考えて1音下げにしたんだと思いますが。
ということで、ここのブログのイエスタデイは、BOSSのAC-3とDROPTUNEという虚飾で塗り固められた曲(笑)なのですが、そういったことを伏せて聴いた時にどれだけの人が、そのことに気が付くのか興味深いところです。
ちょっと話はズレますが、よくテレビのヴァラエティ番組で3、4万円のヴァイオリンと億単位の価値があるストラディヴァリウスの音をブラインドテストで聴き当てるとかっていう企画をやると、そこそこ知識をもった人でも、こっちの方がいい音とかいって安物のヴァイオリンを選ぶことがありますが、人の判断基準なんて結構いい加減というか感覚的ですよね。
ブランドに弱かったり、偏見でモノをみたり、高いものがいいものという理論にとらわれて、本質を見抜けない人は意外と多いですね。まあ、僕のことですけど。
このブログは今のところノーマルチューニングの曲が大半なので、DROPTUNEも当分の間は出番はないと思いますが、今後ハードロック等やる場合に登場するかもしれません。
Posted by cha-key at
◆2011年02月24日22:35
│機材公開