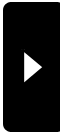スポンサーリンク
第21回 BOSS AC-3
機材紹介第6弾です。今回は、このブログでも度々活躍しているエフェクターを紹介します。
BOSSのAC-3です。

いわゆるアコースティックシミュレーターというやつです。
こんなシミュレーターものなんか使用せずにちゃんとアコギを弾けという声も聞こえてきそうですね。
ちゃんとしたアコーステックギターも所有していますが、夜中に鳴らす事なんてとてもできないので、まったくもって活躍の場がありません。
このエフェクターを通すとエレキギターで弾いた音がアコースティックギターの音になります。
といっても、セッティング次第という感じですね。
マニュアルをみるとシングルコイルのピックアップで弾くとニュアンスが出るとあります。
しかもフロントピックアップがいいみたいです。
現在メインのギターのピックアップはHSH構成の3ピックアップです。
ハーフポジションはコイルタップでハムバッカーがシングルになるので、フロントとセンターのミックスポジションで弾くと一番それらしい音になります。
ここのブログにあるビートルズのイエスタデイやインマイライフ、バッハのリュート組曲はこのエフェクターを使って録りました。
あとBOØWYのLIAR GIRLのバッキングでも裏で小さく鳴っています。
まあ大体こんな感じの音になるということです。
これをアコギの音と捉えるかどうかは人によって差があると思いますが、個人的にはアコギといわれればアコギかなぁ?というレベルです。
シャリシャリ気味のセッティングにしてありますが、ツマミをいじってやれば、もう少し丸みのある音も出せます。
購入価格5,000円ということを考えればいい買い物だったと思います。
まだまだお世話になるだろうなぁ。
BOSSのAC-3です。
いわゆるアコースティックシミュレーターというやつです。
こんなシミュレーターものなんか使用せずにちゃんとアコギを弾けという声も聞こえてきそうですね。
ちゃんとしたアコーステックギターも所有していますが、夜中に鳴らす事なんてとてもできないので、まったくもって活躍の場がありません。
このエフェクターを通すとエレキギターで弾いた音がアコースティックギターの音になります。
といっても、セッティング次第という感じですね。
マニュアルをみるとシングルコイルのピックアップで弾くとニュアンスが出るとあります。
しかもフロントピックアップがいいみたいです。
現在メインのギターのピックアップはHSH構成の3ピックアップです。
ハーフポジションはコイルタップでハムバッカーがシングルになるので、フロントとセンターのミックスポジションで弾くと一番それらしい音になります。
ここのブログにあるビートルズのイエスタデイやインマイライフ、バッハのリュート組曲はこのエフェクターを使って録りました。
あとBOØWYのLIAR GIRLのバッキングでも裏で小さく鳴っています。
まあ大体こんな感じの音になるということです。
これをアコギの音と捉えるかどうかは人によって差があると思いますが、個人的にはアコギといわれればアコギかなぁ?というレベルです。
シャリシャリ気味のセッティングにしてありますが、ツマミをいじってやれば、もう少し丸みのある音も出せます。
購入価格5,000円ということを考えればいい買い物だったと思います。
まだまだお世話になるだろうなぁ。
Posted by cha-key at
◆2011年01月15日17:38
│機材公開
第18回 FrontierDesign AlphaTrack
いやー、冷えてきました。高山では雪が積もったみたいですね。
これからの時期、セーフティドライブでいきたいものです。
さて、第18回目の今回は機材紹介第5弾をお送りします。
今回はギター関係からは少し離れて、レコーディング/ミックス関係の機材を紹介します。
ここにアップしている曲はコンピュータを使用してレコーディングしています。
実際に経験のある人は分かると思うのですが、いざ録音を開始する際に、RECボタンを押したり、曲の頭出し等をするのにマウスでカーソルを移動させてクリックとか、曲のミックス作業の際にマウスでドラッグしてフェーダーを動かすのって非常に煩わしさを感じます。
ギターを抱えて、ピックを握ったまま、コンピュータを操作するのって結構大変なんですよ。
最初は我慢してやっていたのですが、曲中で各パートの音量レベルやパンを変化させたり、エフェクトのオンオフをするオートメーションデータを描く際に素早い動作が必要とされる時にマウスではどうしてもタイミングが取れず思うようなデータが描けず何回もやりなおしということがありました。そこで今回紹介する機材を導入しました。

Frontier Design AlphaTrackという機材です。
これはフィジカルコントローラーというものになります。
見てのとおり再生、録音、停止、早送り、巻き戻しの各ボタン、左端にある1本の100mmフェーダー、上部にある3つのエンコーダつまみ等の必要最小限なものしか用意されていませんが、自分としてはそれほど難しい操作は必要としていないのでコレだけあれば十分です。
フェーダーが何本も並んだ大型のミキサー型のフィジカルコントローラーに憧れもありますが、使いこなせないし、それ以前に部屋に置く場所がありません。
MTR感覚でボタン操作1つで作業が進められるのは非常に快適です。
上部にある液晶画面には、コンピュータ上で各トラックにネーミングしたトラックネーム(vocal,lead guitar,bass等)が表示されるので、今、どのトラックが選択されているかも一目で分かるし、ファンクションキーによく使用する操作をアサインしておくこともできます。フェーダーはムーヴィングフェーダーなので、曲の進行にあわせて記録されたとおりにフェーダーが動きます。ちょっとプロっぽい感覚が味わえます。
コンピュータとはUSB接続のみで電源供給ができ、単独で別電源が要らないものも必要以上に机の上がゴチャゴチャしないのでポイントが高いです。
意外に使えるのが下部にあるリボンコントローラです。ここに指をのせて、指を左右に動かす事で早送り、巻き戻しと同じ操作ができるのは非常に便利です。
以下のデモビデオで大体の感じがつかめると思います。うちのアプリはcubaseじゃなくてlogicですが。
難点といえば、ボタンを押した感じが少し安っぽく、押し方によって反応しないことがよくあります。でも、これについては中古だからかもしれませんね。
あと、フェーダーの精度がいまいちで0.1dB単位での調整ができないことがあります。
まあ、ボクには0.1dBの違いなんて分からないので何も問題はないのですが。
オークションで17,000円で入手しましたが高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれだと思います。
でも、これを導入したことで宅録作業の効率は随分と改善されたと思います。
あと10曲もミックスできれば元は取れそうかな。まあ、がんばってみます。それでは、また次回!
これからの時期、セーフティドライブでいきたいものです。
さて、第18回目の今回は機材紹介第5弾をお送りします。
今回はギター関係からは少し離れて、レコーディング/ミックス関係の機材を紹介します。
ここにアップしている曲はコンピュータを使用してレコーディングしています。
実際に経験のある人は分かると思うのですが、いざ録音を開始する際に、RECボタンを押したり、曲の頭出し等をするのにマウスでカーソルを移動させてクリックとか、曲のミックス作業の際にマウスでドラッグしてフェーダーを動かすのって非常に煩わしさを感じます。
ギターを抱えて、ピックを握ったまま、コンピュータを操作するのって結構大変なんですよ。
最初は我慢してやっていたのですが、曲中で各パートの音量レベルやパンを変化させたり、エフェクトのオンオフをするオートメーションデータを描く際に素早い動作が必要とされる時にマウスではどうしてもタイミングが取れず思うようなデータが描けず何回もやりなおしということがありました。そこで今回紹介する機材を導入しました。
Frontier Design AlphaTrackという機材です。
これはフィジカルコントローラーというものになります。
見てのとおり再生、録音、停止、早送り、巻き戻しの各ボタン、左端にある1本の100mmフェーダー、上部にある3つのエンコーダつまみ等の必要最小限なものしか用意されていませんが、自分としてはそれほど難しい操作は必要としていないのでコレだけあれば十分です。
フェーダーが何本も並んだ大型のミキサー型のフィジカルコントローラーに憧れもありますが、使いこなせないし、それ以前に部屋に置く場所がありません。
MTR感覚でボタン操作1つで作業が進められるのは非常に快適です。

上部にある液晶画面には、コンピュータ上で各トラックにネーミングしたトラックネーム(vocal,lead guitar,bass等)が表示されるので、今、どのトラックが選択されているかも一目で分かるし、ファンクションキーによく使用する操作をアサインしておくこともできます。フェーダーはムーヴィングフェーダーなので、曲の進行にあわせて記録されたとおりにフェーダーが動きます。ちょっとプロっぽい感覚が味わえます。
コンピュータとはUSB接続のみで電源供給ができ、単独で別電源が要らないものも必要以上に机の上がゴチャゴチャしないのでポイントが高いです。
意外に使えるのが下部にあるリボンコントローラです。ここに指をのせて、指を左右に動かす事で早送り、巻き戻しと同じ操作ができるのは非常に便利です。
以下のデモビデオで大体の感じがつかめると思います。うちのアプリはcubaseじゃなくてlogicですが。
難点といえば、ボタンを押した感じが少し安っぽく、押し方によって反応しないことがよくあります。でも、これについては中古だからかもしれませんね。
あと、フェーダーの精度がいまいちで0.1dB単位での調整ができないことがあります。
まあ、ボクには0.1dBの違いなんて分からないので何も問題はないのですが。
オークションで17,000円で入手しましたが高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれだと思います。
でも、これを導入したことで宅録作業の効率は随分と改善されたと思います。
あと10曲もミックスできれば元は取れそうかな。まあ、がんばってみます。それでは、また次回!
Posted by cha-key at
◆2010年12月10日00:02
│機材公開
第16回 YAMAHA Magicstomp
機材紹介第4弾です。
毎度そうのですがエフェクターに興味の無い人は今回のトピックはパスしたほうがいいと思います。
今回はヤマハのMagic stomp(マジックストンプ)というかなりマニアックなエフェクターを紹介します。ちょっと長文です。

このエフェクターは本当に癖のあるエフェクターで、個人的には人にはとても勧められません。
カテゴライズするならばマルチエフェクターということになるんでしょうが、普通のマルチエフェクターとは明らかに異なります。
通常のマルチエフェクターはコンプ、歪み、揺れもの系、残響系の必要なものだけを自分でチョイスしてプログラムすることができますが、マジックストンプは、必要なものだけをチョイスするという概念がありません。
歪み、コーラス、フランジャー、ディレイ等単体のみのプログラムは用意されているのですが、それらを組み合わせたものは、もともと用意されているプリセットパターンから選ぶしかないのです。
うーん、なんか伝えにくいですね。例えば、歪みとコーラスを同時にかけたい場合、歪み+コーラスというパターンがあればそれをチョイスしてやればいいのですが、さらに、ディレイとリバープも追加してかけたいとなった時に、歪み+コーラス+ディレイ+リバーブというパターンがプリセットに用意されていない場合は、あきらめるしかないのです。何とも信じがたい仕様です。(まあ一般的に使いそうな組み合わせは大体カバーしていますが)
おまけにプログラムチェンジをするとかなり目立つ音切れが生じます。(単純にエフェクトのON,OFFなら大丈夫。)
最も致命的なのは、それぞれのエフェクトには設定できるパラメータが10種類以上あるのですが、本体から操作できるパラメータはたったの3つだけです。これってどうゆうことですか??製品としておかしくないですか??世界のYAMAHAの製品でしょ??
もともとこのエフェクターはUSB経由でPCに接続することを前提に作られていて、細かい設定はPC側で行うようになっていたようです。でも、パラメータをいじるのに、いちいちPCにつなぐなんて面倒なことをする人がどれだけいるのでしょうか?
しかもエディットソフトのアップデートもわずか数年で終了し、ウィンドウズXP以前のOSじゃないと動かないようです。マックにおいてはOS9じゃないと動かないようです。完全にケンカを売ってますね。
とりあえずソフトウエアがバージョン2になり、ようやくマジックストンプ本体からすべてのパラメータを操作できるようになりました。
じゃあ、こんなエフェクターを何故に売却せずに所有しているのか?という話になると思いますが、その理由は内蔵されているエフェクトにBOφWYの曲を演奏するのにどうしても必要なものがあるからです。
リバースゲートっていうリバーブなんですが、「ヒューアー」という独特な反響音が作り出せます。
有名なところではライブバージョンのマリオネットのギターソロで前半から後半に移る際に鳴っているアレです。といってもどれだけの人に伝わるか分かりませんが。
ここのブログの過去曲ではメモリーのイントロの歌入り直前と間奏後の歌入り直前、ファニーボーイのギターソロの一番最後に使用しています。よかったら聴いて確認してみてください。
もともとは布袋さんをはじめ数々のプロの方も愛用していたヤマハのラックエフェクターの名機SPX900に入っていたエフェクトなのですが、コンパクトエフェクターでリバースゲートが使えたらいいなあと思い、いろいろと探してみた結果、たどり着いたのがマジックストンプでした。
リバースゲートのためだけにマジックストンプを所有しているといっても過言ではありません。
散々、酷評してきたマジックストンプですが、悪いところばかりではありません。
先ほど話に挙ったSPXシリーズがプロ御用達の機材である(であった?)ことから分かるようにヤマハの空間系エフェクトのクオリティは非常に高いのです。
マルチエフェクターとして考えず、リバーブ、ディレイ、コーラス、フェーザー、アンプシミュレーターという単体のエフェクターとして割り切って考えれば、結構よいエフェクターかもしれません。(本当か?)
マジックストンプという名のとおり、マルチエフェクターではなく「何にでも化けるストンプボックス」というのが、きっと製品コンセプトなのでしょう。
これまで散々述べてきた圧倒的なまでの短所に隠れがちですがディレイも8タップディレイとか普通じゃない機能があったり、アコーステックギターとの相性がよかったりといった魅力もあり、ネット上で調べてみると意外と評価している人もいます。特に海外での評価が高いみたいです。
以上、ダラダラと書いてしまいました。決して人にはお勧めしませんが、かといって、どうしようもないエフェクターの一言で終わらしてしまうのも何か違うような不思議な魅力があります。生産終了品で中古しか出回っていませんが、使う勇気のある人は是非買ってみて下さい。
毎度そうのですがエフェクターに興味の無い人は今回のトピックはパスしたほうがいいと思います。
今回はヤマハのMagic stomp(マジックストンプ)というかなりマニアックなエフェクターを紹介します。ちょっと長文です。
このエフェクターは本当に癖のあるエフェクターで、個人的には人にはとても勧められません。
カテゴライズするならばマルチエフェクターということになるんでしょうが、普通のマルチエフェクターとは明らかに異なります。
通常のマルチエフェクターはコンプ、歪み、揺れもの系、残響系の必要なものだけを自分でチョイスしてプログラムすることができますが、マジックストンプは、必要なものだけをチョイスするという概念がありません。
歪み、コーラス、フランジャー、ディレイ等単体のみのプログラムは用意されているのですが、それらを組み合わせたものは、もともと用意されているプリセットパターンから選ぶしかないのです。

うーん、なんか伝えにくいですね。例えば、歪みとコーラスを同時にかけたい場合、歪み+コーラスというパターンがあればそれをチョイスしてやればいいのですが、さらに、ディレイとリバープも追加してかけたいとなった時に、歪み+コーラス+ディレイ+リバーブというパターンがプリセットに用意されていない場合は、あきらめるしかないのです。何とも信じがたい仕様です。(まあ一般的に使いそうな組み合わせは大体カバーしていますが)
おまけにプログラムチェンジをするとかなり目立つ音切れが生じます。(単純にエフェクトのON,OFFなら大丈夫。)
最も致命的なのは、それぞれのエフェクトには設定できるパラメータが10種類以上あるのですが、本体から操作できるパラメータはたったの3つだけです。これってどうゆうことですか??製品としておかしくないですか??世界のYAMAHAの製品でしょ??
もともとこのエフェクターはUSB経由でPCに接続することを前提に作られていて、細かい設定はPC側で行うようになっていたようです。でも、パラメータをいじるのに、いちいちPCにつなぐなんて面倒なことをする人がどれだけいるのでしょうか?
しかもエディットソフトのアップデートもわずか数年で終了し、ウィンドウズXP以前のOSじゃないと動かないようです。マックにおいてはOS9じゃないと動かないようです。完全にケンカを売ってますね。

とりあえずソフトウエアがバージョン2になり、ようやくマジックストンプ本体からすべてのパラメータを操作できるようになりました。
じゃあ、こんなエフェクターを何故に売却せずに所有しているのか?という話になると思いますが、その理由は内蔵されているエフェクトにBOφWYの曲を演奏するのにどうしても必要なものがあるからです。
リバースゲートっていうリバーブなんですが、「ヒューアー」という独特な反響音が作り出せます。
有名なところではライブバージョンのマリオネットのギターソロで前半から後半に移る際に鳴っているアレです。といってもどれだけの人に伝わるか分かりませんが。
ここのブログの過去曲ではメモリーのイントロの歌入り直前と間奏後の歌入り直前、ファニーボーイのギターソロの一番最後に使用しています。よかったら聴いて確認してみてください。
もともとは布袋さんをはじめ数々のプロの方も愛用していたヤマハのラックエフェクターの名機SPX900に入っていたエフェクトなのですが、コンパクトエフェクターでリバースゲートが使えたらいいなあと思い、いろいろと探してみた結果、たどり着いたのがマジックストンプでした。
リバースゲートのためだけにマジックストンプを所有しているといっても過言ではありません。
散々、酷評してきたマジックストンプですが、悪いところばかりではありません。

先ほど話に挙ったSPXシリーズがプロ御用達の機材である(であった?)ことから分かるようにヤマハの空間系エフェクトのクオリティは非常に高いのです。
マルチエフェクターとして考えず、リバーブ、ディレイ、コーラス、フェーザー、アンプシミュレーターという単体のエフェクターとして割り切って考えれば、結構よいエフェクターかもしれません。(本当か?)
マジックストンプという名のとおり、マルチエフェクターではなく「何にでも化けるストンプボックス」というのが、きっと製品コンセプトなのでしょう。
これまで散々述べてきた圧倒的なまでの短所に隠れがちですがディレイも8タップディレイとか普通じゃない機能があったり、アコーステックギターとの相性がよかったりといった魅力もあり、ネット上で調べてみると意外と評価している人もいます。特に海外での評価が高いみたいです。
以上、ダラダラと書いてしまいました。決して人にはお勧めしませんが、かといって、どうしようもないエフェクターの一言で終わらしてしまうのも何か違うような不思議な魅力があります。生産終了品で中古しか出回っていませんが、使う勇気のある人は是非買ってみて下さい。
Posted by cha-key at
◆2010年11月13日23:52
│機材公開
第14回 T.C.ELECTRONIC G-SYSTEM
機材紹介第3弾です。今回は、ある意味、ボクのギターシステムの核になっているT.C.ELECTRONICのG-SYSTEMについて紹介します。

はっきりいって、ボクなんかが所有していることは許されない完全プロ仕様のとんでもない代物です。ユーザーもSTEVE VAI、LUNA SEAのSUGIZOさん等、そうそうたるメンツ。発売から随分経ちますが、未だにT.C.ELECTRONICのギターエフェクターのフラッグシップに君臨しています。値段の方も実勢価格で178,000円と完全プロ仕様になっています。専用の巨大エフェクターボードとアクリル板のフロントパネル込みの中古品をオークションで入手したのですが、それなりの値段がしました。
正直なところ、全機能のおそらく10分の1程度しか使っておらす、まったくもって猫に小判状態です。でも1つ1つのエフェクトのクオリティが高く、そこは恩恵を受けているかと思います。サウンドクオリティだけで考えれば、プロが使おうがアマチュアが使おうが関係ないですからね。(もちろん周辺機器とあわせてクオリティを極限まで引き出すという技術はあるのでしょうが)
とにかくコーラス、フェイザー、ディレイ、リバーブ等は以前使用していた機器と比較してワンランク上の音がします。なんというかイヤミな感じがなく上品な感じがします。ワウやワーミー、インテリジェントピッチシフターの効きも自然な感じがいいです。
サウンドクオリティはこちらで確認してください。(例によって自分で動画撮影はできませんのですみません)
よく機材マニアの人が、こういったマルチエフェクターは面白みがないとか、オリジナリティがないとかって意見していますが、ボクはもともとマルチエフェクターから入ったクチなので、あまり気になりません。確かにコンパクトエフェクターは直感的に操作ができるし、プロミュージシャンのようにエフェクターボードに自分の好みの機材を所狭しと並べるのは、男心をくすぐられます。
ボクも一時期、コンパクトエフェクターでシステムを組んでみようと試したこともあるのですが、結局、エフェクターを揃えたり、スイッチングシステムやパッチケーブルやパワーサプライのことを考えると、割高になるし、配線が複雑になればトラブルも増えるし、色々考えて今のシステムにしました。(MIDIにより以前紹介したヤマハのアンプをコントロールできるのも大きなポイントでした。)
音色設定は本体での設定はもちろんUSBケーブルでコンピュータ側から設定できるのも他のエフェクターと違う点だと思います。コンピュータの大きい画面で設定できるのは非常に便利です。本体の小さい液晶パネルを見ながらチマチマ設定するのは疲れます。これが嫌でマルチエフェクターが嫌いという人もいるのでは?
あと、頑丈、壊れにくいのも機材にとって大事なポイントですよね。G・SYSTEMはプロの過酷なツアーにも耐えられるようアルミ削りだしのボディとなっているのですが、コレに関しては、もう笑うしかないとっておきの映像があります。
どうですか?とても日本人じゃ思いつかない発想ですよね。いくらなんでもやり過ぎでしょう。戦場でライブをする人がいるのでしょうか?大沢親分ではありませんが、とにかくあっぱれな映像です。
高価な物だからこそ、できるだけたくさん使って元をとらなきゃいけませんね。奥が深い機器なので、時間をみつけて勉強したいと思います。
はっきりいって、ボクなんかが所有していることは許されない完全プロ仕様のとんでもない代物です。ユーザーもSTEVE VAI、LUNA SEAのSUGIZOさん等、そうそうたるメンツ。発売から随分経ちますが、未だにT.C.ELECTRONICのギターエフェクターのフラッグシップに君臨しています。値段の方も実勢価格で178,000円と完全プロ仕様になっています。専用の巨大エフェクターボードとアクリル板のフロントパネル込みの中古品をオークションで入手したのですが、それなりの値段がしました。
正直なところ、全機能のおそらく10分の1程度しか使っておらす、まったくもって猫に小判状態です。でも1つ1つのエフェクトのクオリティが高く、そこは恩恵を受けているかと思います。サウンドクオリティだけで考えれば、プロが使おうがアマチュアが使おうが関係ないですからね。(もちろん周辺機器とあわせてクオリティを極限まで引き出すという技術はあるのでしょうが)
とにかくコーラス、フェイザー、ディレイ、リバーブ等は以前使用していた機器と比較してワンランク上の音がします。なんというかイヤミな感じがなく上品な感じがします。ワウやワーミー、インテリジェントピッチシフターの効きも自然な感じがいいです。
サウンドクオリティはこちらで確認してください。(例によって自分で動画撮影はできませんのですみません)
よく機材マニアの人が、こういったマルチエフェクターは面白みがないとか、オリジナリティがないとかって意見していますが、ボクはもともとマルチエフェクターから入ったクチなので、あまり気になりません。確かにコンパクトエフェクターは直感的に操作ができるし、プロミュージシャンのようにエフェクターボードに自分の好みの機材を所狭しと並べるのは、男心をくすぐられます。
ボクも一時期、コンパクトエフェクターでシステムを組んでみようと試したこともあるのですが、結局、エフェクターを揃えたり、スイッチングシステムやパッチケーブルやパワーサプライのことを考えると、割高になるし、配線が複雑になればトラブルも増えるし、色々考えて今のシステムにしました。(MIDIにより以前紹介したヤマハのアンプをコントロールできるのも大きなポイントでした。)
音色設定は本体での設定はもちろんUSBケーブルでコンピュータ側から設定できるのも他のエフェクターと違う点だと思います。コンピュータの大きい画面で設定できるのは非常に便利です。本体の小さい液晶パネルを見ながらチマチマ設定するのは疲れます。これが嫌でマルチエフェクターが嫌いという人もいるのでは?
あと、頑丈、壊れにくいのも機材にとって大事なポイントですよね。G・SYSTEMはプロの過酷なツアーにも耐えられるようアルミ削りだしのボディとなっているのですが、コレに関しては、もう笑うしかないとっておきの映像があります。
どうですか?とても日本人じゃ思いつかない発想ですよね。いくらなんでもやり過ぎでしょう。戦場でライブをする人がいるのでしょうか?大沢親分ではありませんが、とにかくあっぱれな映像です。
高価な物だからこそ、できるだけたくさん使って元をとらなきゃいけませんね。奥が深い機器なので、時間をみつけて勉強したいと思います。
Posted by cha-key at
◆2010年10月20日02:13
│機材公開
第11回 YAMAHA DG100-212A
さて、機材紹介第2弾ですが、今回はギターアンプを紹介します。
現在所有しているギターアンプはYAMAHA DG100-212Aです。

今年の1月にネットオークションで38,000円で入手しました。
確か1997、8年くらいに発売され、当時定価が198,000円だったと思います。実はその当時、ライブ用に購入を検討しており、札束を用意して楽器屋で試奏までしたので結構細かく覚えています。実際に使用してみて、メチャクチャ気に入ったのですが、アンプにそれだけの金を出すなら、その金を他のことに回したい気持ちや、普段コレだけデカイものを鳴らせるような環境がなかったこともあり、随分悩んだのですが、結局、その時は25,000円くらいの掘り出し物のグヤトーンの中古チューブアンプを買いました。
そんな経緯もあり、ネットオークションで見つけた時、38,000円という値段も手伝って、ついついポチッとやってしまいました。
DG100はチューブの動作をシミュレートした、いわゆるデジタルモデリングアンプってヤツですが、各音域のノブを動かすと他の音域にも影響が出たり、ノイズまで再現する等のこだわりの一品となっています。
デジタルモデリングアンプというと、まがい物というイメージで敬遠されがちですが、コレに関してはかなりイイ線いっていると思います。少なくとも僕の耳にはチューブアンプの音として聞こえます。ギターのボリュームやピッキングニュアンス等に対するレスポンスもいいと思います。かのアランホールズワースやリッチーコッツェン、野呂一生さんが使用していたことからもクオリティの高さは伺い知ることができます。
本当は自分で弾いて音質について紹介すべきなのでしょうが、動画を撮るスキルがないため(というかやる気がないため)、YouTube上の同機種シリーズのDG1000の動画でお茶を濁します。
全部で8つのアンプモデルが搭載されています。(リード1、2、ドライブ1、2、クランチ1、2、クリーン1、2)個人的にはドライブ2とクリーン2の音の太さがツボです。歪みはそれほど強くありません。マーシャル程度だと思います。ブギーやソルダーノのようなハイゲインな音は出ません。まあ、個人的には十分な歪みです。
操作性ですが、デジタルのメリットで気に入ったセッティングを128種類プログラムすることができます。まあ、実際に使用するのは10種類もあれば十分ですけど。
そして、このプログラムチェンジの瞬間こそがDG100の真骨頂です。プログラムチェンジすると、変わるのは音色だけではなく、なんと各ノブも設定位置までモータードライブで回転します。これもYouTube上の動画を見てください。
コレを見ているだけでかなり楽しめます。はっきり言ってノブが自動で動いたところで、ミキサーのオートフェーダーのような便利さはないと思いますが、それでも今現在のアンプセッティングが視覚的に確認できるのは非常に安心できます。
あと気に入っているところは、レトロなルックスですね。色合いも好みです。部屋の中で結構な場所をとっていますが、個人的にはインテリアの一部として見ることができます。(家族には邪魔なだけみたいですが)
普段の録音時はスピーカーシミュレータ端子からコンピュータ接続していますが、音が出せる時間帯には実際に鳴らして楽しんでいます。それでもパワーがありすぎて、アウトプットレベル1以下での使用になっています。
生産終了してから随分と経つので故障が心配ですが、丁寧に扱い末永く使っていきたい一品です。
現在所有しているギターアンプはYAMAHA DG100-212Aです。
今年の1月にネットオークションで38,000円で入手しました。
確か1997、8年くらいに発売され、当時定価が198,000円だったと思います。実はその当時、ライブ用に購入を検討しており、札束を用意して楽器屋で試奏までしたので結構細かく覚えています。実際に使用してみて、メチャクチャ気に入ったのですが、アンプにそれだけの金を出すなら、その金を他のことに回したい気持ちや、普段コレだけデカイものを鳴らせるような環境がなかったこともあり、随分悩んだのですが、結局、その時は25,000円くらいの掘り出し物のグヤトーンの中古チューブアンプを買いました。
そんな経緯もあり、ネットオークションで見つけた時、38,000円という値段も手伝って、ついついポチッとやってしまいました。
DG100はチューブの動作をシミュレートした、いわゆるデジタルモデリングアンプってヤツですが、各音域のノブを動かすと他の音域にも影響が出たり、ノイズまで再現する等のこだわりの一品となっています。
デジタルモデリングアンプというと、まがい物というイメージで敬遠されがちですが、コレに関してはかなりイイ線いっていると思います。少なくとも僕の耳にはチューブアンプの音として聞こえます。ギターのボリュームやピッキングニュアンス等に対するレスポンスもいいと思います。かのアランホールズワースやリッチーコッツェン、野呂一生さんが使用していたことからもクオリティの高さは伺い知ることができます。
本当は自分で弾いて音質について紹介すべきなのでしょうが、動画を撮るスキルがないため(というかやる気がないため)、YouTube上の同機種シリーズのDG1000の動画でお茶を濁します。
全部で8つのアンプモデルが搭載されています。(リード1、2、ドライブ1、2、クランチ1、2、クリーン1、2)個人的にはドライブ2とクリーン2の音の太さがツボです。歪みはそれほど強くありません。マーシャル程度だと思います。ブギーやソルダーノのようなハイゲインな音は出ません。まあ、個人的には十分な歪みです。
操作性ですが、デジタルのメリットで気に入ったセッティングを128種類プログラムすることができます。まあ、実際に使用するのは10種類もあれば十分ですけど。
そして、このプログラムチェンジの瞬間こそがDG100の真骨頂です。プログラムチェンジすると、変わるのは音色だけではなく、なんと各ノブも設定位置までモータードライブで回転します。これもYouTube上の動画を見てください。
コレを見ているだけでかなり楽しめます。はっきり言ってノブが自動で動いたところで、ミキサーのオートフェーダーのような便利さはないと思いますが、それでも今現在のアンプセッティングが視覚的に確認できるのは非常に安心できます。
あと気に入っているところは、レトロなルックスですね。色合いも好みです。部屋の中で結構な場所をとっていますが、個人的にはインテリアの一部として見ることができます。(家族には邪魔なだけみたいですが)
普段の録音時はスピーカーシミュレータ端子からコンピュータ接続していますが、音が出せる時間帯には実際に鳴らして楽しんでいます。それでもパワーがありすぎて、アウトプットレベル1以下での使用になっています。
生産終了してから随分と経つので故障が心配ですが、丁寧に扱い末永く使っていきたい一品です。
Posted by cha-key at
◆2010年09月20日00:20
│機材公開