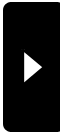スポンサーリンク
第47回 Eric Johnson Stratocaster
昨日、このブログのアクセス数が、30,000を超えました。
去年の9月に10,000だったので、1年間で20,000のアクセスがあったことになります。
月に1回更新するかどうかという超スローペースなブログですが、見ていただけるのはありがたいことです。
さて、第47回目である今回は機材紹介ということで、前々回のGuitar Loves Youで使用したギターであるFender USA Eric Johnson signature Stratocasterを紹介をします。
前々回のトピックの中でフェンダーUSA エリックジョンソン シグネイチャーモデル ストラトキャスターを使用したことは触れました。
実は2年程前からストラト欲しい病を患い、いろいろ物色していました。
カスタムショップのものや、ストラトプロ等も検討しました。
途中、脱線して、こんなものを買ってしまったので、ストラト購入への道が遠のいてしまいました。
でも、やっぱり欲しいものは欲しい。
そんなことを思っていた矢先、このストラトに出会いました。
今さらシグネイチャーモデルを使う事に抵抗もあったのですが、ミュージシャンズ・ミュージシャンといわれるエリックジョンソンが監修した実用的なスペックをもっていること。
シグネイチャーモデルといいつつも、パッと見、全く普通のストラトと変わらないこと。
なにより新品同様で10万円以下であったこと。
ということで、2011年11月に、めでたく念願の人生初ストラトを入手しました。

さて、このエリックジョンソンストラトですが、先ほど触れた通り、見た目は全く普通のストラトなのですが、細かい部分でカスタマイズされています。
まずネックですが、57年製ストラトがベースになっているため、V字型ネックなのですが、ボディ側に近づくにつれ、徐々にU字型に変化していくという変わった作りになっています。
V字型ネックというのは初めてで、太いので握りにくいかな?と思っていたのですが、意外と収まりがよく、手にフィットして弾きやすく感じます。
フィンガーボードですが、通常のストラトよりフィンガーボードの面がフラットになっています。これにより通常のストラトにありがちなハイフレットでのベンディング時の音切れが解消されています。
フィンガーボード上には全体的に奇麗なトラ目が出ており、カスタムショップ製ではないにしろ、材にこだわっていることが感じ取れます。
フレットも通常のストラトとは違い、ミディアムジャンボが打たれています。
今まで太めのフレットのギターばかり弾いてきたので、その点に関しては違和感なく弾けます。

ボディですが、アルダー材で、ボディバックのコンターも通常のストラトより深くなっており、体にフィットします。
ヘッドも通常のストラトより薄めに作られているようで、薄くなった分、弦のテンションを稼ぐ事ができるため、1、2弦のテンションピンがセットされていません。
弦との接点が少なくなる分、チューニングの安定や、サスティンにも影響があるのではないかと思います。
ピックアップはエリックジョンソン自身が監修したオリジナルピックアップが搭載されています。
通常、ストラトのトーンコントロールはセンター用とフロント用となっていますが、このモデルはリア用とフロント用に結線されています。
しかし、人生初、ストラトということもあり、あえて通常のセンター&フロントに結線し直しました。
(エリックジョンソンの曲が弾きたくて、購入したわけではないということも理由としてあります。まあ、弾きたくても弾けませんが )
)
今後、いろいろ試してみて、リア&フロントに戻すかもしれませんが。

生音もよく鳴り、チューニングも安定しているし、上記のように細かくカスタマイズされているので、個人的には弾きやすいギターだと思います。
今後のレコーディングにもボチボチと使っていきたいですね。
去年の9月に10,000だったので、1年間で20,000のアクセスがあったことになります。
月に1回更新するかどうかという超スローペースなブログですが、見ていただけるのはありがたいことです。
さて、第47回目である今回は機材紹介ということで、前々回のGuitar Loves Youで使用したギターであるFender USA Eric Johnson signature Stratocasterを紹介をします。
前々回のトピックの中でフェンダーUSA エリックジョンソン シグネイチャーモデル ストラトキャスターを使用したことは触れました。
実は2年程前からストラト欲しい病を患い、いろいろ物色していました。
カスタムショップのものや、ストラトプロ等も検討しました。
途中、脱線して、こんなものを買ってしまったので、ストラト購入への道が遠のいてしまいました。
でも、やっぱり欲しいものは欲しい。
そんなことを思っていた矢先、このストラトに出会いました。
今さらシグネイチャーモデルを使う事に抵抗もあったのですが、ミュージシャンズ・ミュージシャンといわれるエリックジョンソンが監修した実用的なスペックをもっていること。
シグネイチャーモデルといいつつも、パッと見、全く普通のストラトと変わらないこと。
なにより新品同様で10万円以下であったこと。
ということで、2011年11月に、めでたく念願の人生初ストラトを入手しました。
さて、このエリックジョンソンストラトですが、先ほど触れた通り、見た目は全く普通のストラトなのですが、細かい部分でカスタマイズされています。
まずネックですが、57年製ストラトがベースになっているため、V字型ネックなのですが、ボディ側に近づくにつれ、徐々にU字型に変化していくという変わった作りになっています。
V字型ネックというのは初めてで、太いので握りにくいかな?と思っていたのですが、意外と収まりがよく、手にフィットして弾きやすく感じます。
フィンガーボードですが、通常のストラトよりフィンガーボードの面がフラットになっています。これにより通常のストラトにありがちなハイフレットでのベンディング時の音切れが解消されています。
フィンガーボード上には全体的に奇麗なトラ目が出ており、カスタムショップ製ではないにしろ、材にこだわっていることが感じ取れます。
フレットも通常のストラトとは違い、ミディアムジャンボが打たれています。
今まで太めのフレットのギターばかり弾いてきたので、その点に関しては違和感なく弾けます。
ボディですが、アルダー材で、ボディバックのコンターも通常のストラトより深くなっており、体にフィットします。
ヘッドも通常のストラトより薄めに作られているようで、薄くなった分、弦のテンションを稼ぐ事ができるため、1、2弦のテンションピンがセットされていません。
弦との接点が少なくなる分、チューニングの安定や、サスティンにも影響があるのではないかと思います。
ピックアップはエリックジョンソン自身が監修したオリジナルピックアップが搭載されています。
通常、ストラトのトーンコントロールはセンター用とフロント用となっていますが、このモデルはリア用とフロント用に結線されています。
しかし、人生初、ストラトということもあり、あえて通常のセンター&フロントに結線し直しました。
(エリックジョンソンの曲が弾きたくて、購入したわけではないということも理由としてあります。まあ、弾きたくても弾けませんが
 )
)今後、いろいろ試してみて、リア&フロントに戻すかもしれませんが。
生音もよく鳴り、チューニングも安定しているし、上記のように細かくカスタマイズされているので、個人的には弾きやすいギターだと思います。
今後のレコーディングにもボチボチと使っていきたいですね。
Posted by cha-key at
◆2012年09月02日21:19
│機材公開
第43回 ROLAND SDE-1000
3月になり、だんだんと暖かくなってきました。
東日本大震災から、間もなく1年を迎えようとしています。
被災地復興ということで、自分も本当に微力ながらも協力をしてきたのですが、最近、少し意識が薄くなりかけていることも事実です。
3・11を目前に控えた今、改めて復興支援というものを考える必要があると思っています。
さて、第43回目である今回は機材紹介ということで、前々回のWORKING MANで使用したディレイについて紹介をします。
あの強烈なSOS(サウンド オン サウンド)とヘリコプターサウンドの正体ですが、1983年にリリースされたROLAND SDE-1000というラック式のデジタルディレイになります。
見ての通り、色使いといい、少し時代を感じさせる雰囲気のエフェクターです。
うーん。自分、まだ小学生ですね。その頃...。
上に乗せてあるEventideのECLIPSEの洗練された感じとは対照的です。

本家である布袋さんは、これの上位機種であるROLAND SDE-2500という機種を使用してみえるようです。
また、布袋さん以外にもROLAND SDE-2500や、さらなる上位機種であるSDE-3000は今でも多くの内外のトッププロのラックの中に納められていることから、このシリーズは、デジタルとはいえ、ある意味、ヴィンテージサウンドとして認められているのかもしれません。
デジタルなのに、その割には柔らかくて暖かみのある音がします。
その辺りがプロに認められている理由なのかもしれません。
このディレイの最大のウリはディレイに、癖のあるモジュレーションをかけられることだと思います。
もしかしたら、最近の機種でも同じことができるのかもしれませんが、コレと同じような質感の音は中々作れません。
自分の設定の仕方がマズいだけかもしれませんが...。
さて、SOSとヘリコプターサウンドについて説明をしますが、実はSDE-1000単体だけでは、あのサウンドは再現できません。
SDE-1000の背面には外部コントロール端子が付いており、フットペダルを接続し、ディレイのON,OFFや、ディレイホールドのON,OFF,プログラムチェンジのコントロールを行うことで、SOSとヘリコプターサウンドを作っています。
ヘリコプターをやるには、ディレイとホールドを同時にONする必要があります。
これを、それぞれ単独のフットペダルでやろうとすると、同時に2つのフットペダルを踏む必要があります。
両足を使って踏む?、レーサーのようにヒールandトゥーで踏む?
どちらにしても、かなり難しい芸当になります。
実際、ギターを弾きながら、同時に2つのフットペダル踏んでも、かなりの確率で失敗し、まともなペリコプターサウンドにはなりません。
布袋さんは英国のエフェクトマイスターであるピートコーニッシュ氏が作製したシステムでフットペダルひとつで、簡単にヘリコプターを飛ばしています。
何とか、あんな風に簡単にできないものかと思い、ネットで調べていく中で、どうもフットペダルの出力に二股のセパレートジャックを使用し、信号を分岐してやるとディレイとホールドを同時にON,OFFできることを知りました。
早速、購入し、試してみるとバッチリできました。
あれだけ苦労してヘリコプターを飛ばしていたのが、嘘のように、簡単に確実に飛ばせることができるようになりました。
あまりに簡単に飛ばせるようになったため、調子に乗って、さらにもう1台SDE-1000を入手し、フットペダルも増設しました。
ということで、現在、うちのSOS・ヘリコプターサウンドのシステムですが、2台のSDE-1000とBOSSのフットペダルFS-6とFS-5Uで構成されています。
見た目は大掛かりな、このシステムですが、ケーブル類も含めても1万円でおつりが出るかなり安上がりな予算で仕上がっています。

前々回のWORKING MANですが、愛用のギターアンプZenTeraのアナログのステレオラインアウトのL、Rそれぞれに1台づつSDE-1000に接続して、SDEの出力をオーディオインターフェイスに送って録音しました。
せっかく苦労して作ったシステムなので、またSOSやヘリコプターサウンドをフューチャーした曲をやりたいと思っています。
東日本大震災から、間もなく1年を迎えようとしています。
被災地復興ということで、自分も本当に微力ながらも協力をしてきたのですが、最近、少し意識が薄くなりかけていることも事実です。
3・11を目前に控えた今、改めて復興支援というものを考える必要があると思っています。
さて、第43回目である今回は機材紹介ということで、前々回のWORKING MANで使用したディレイについて紹介をします。
あの強烈なSOS(サウンド オン サウンド)とヘリコプターサウンドの正体ですが、1983年にリリースされたROLAND SDE-1000というラック式のデジタルディレイになります。
見ての通り、色使いといい、少し時代を感じさせる雰囲気のエフェクターです。
うーん。自分、まだ小学生ですね。その頃...。
上に乗せてあるEventideのECLIPSEの洗練された感じとは対照的です。
本家である布袋さんは、これの上位機種であるROLAND SDE-2500という機種を使用してみえるようです。
また、布袋さん以外にもROLAND SDE-2500や、さらなる上位機種であるSDE-3000は今でも多くの内外のトッププロのラックの中に納められていることから、このシリーズは、デジタルとはいえ、ある意味、ヴィンテージサウンドとして認められているのかもしれません。
デジタルなのに、その割には柔らかくて暖かみのある音がします。
その辺りがプロに認められている理由なのかもしれません。
このディレイの最大のウリはディレイに、癖のあるモジュレーションをかけられることだと思います。
もしかしたら、最近の機種でも同じことができるのかもしれませんが、コレと同じような質感の音は中々作れません。
自分の設定の仕方がマズいだけかもしれませんが...。
さて、SOSとヘリコプターサウンドについて説明をしますが、実はSDE-1000単体だけでは、あのサウンドは再現できません。
SDE-1000の背面には外部コントロール端子が付いており、フットペダルを接続し、ディレイのON,OFFや、ディレイホールドのON,OFF,プログラムチェンジのコントロールを行うことで、SOSとヘリコプターサウンドを作っています。
ヘリコプターをやるには、ディレイとホールドを同時にONする必要があります。
これを、それぞれ単独のフットペダルでやろうとすると、同時に2つのフットペダルを踏む必要があります。
両足を使って踏む?、レーサーのようにヒールandトゥーで踏む?
どちらにしても、かなり難しい芸当になります。
実際、ギターを弾きながら、同時に2つのフットペダル踏んでも、かなりの確率で失敗し、まともなペリコプターサウンドにはなりません。
布袋さんは英国のエフェクトマイスターであるピートコーニッシュ氏が作製したシステムでフットペダルひとつで、簡単にヘリコプターを飛ばしています。
何とか、あんな風に簡単にできないものかと思い、ネットで調べていく中で、どうもフットペダルの出力に二股のセパレートジャックを使用し、信号を分岐してやるとディレイとホールドを同時にON,OFFできることを知りました。
早速、購入し、試してみるとバッチリできました。
あれだけ苦労してヘリコプターを飛ばしていたのが、嘘のように、簡単に確実に飛ばせることができるようになりました。
あまりに簡単に飛ばせるようになったため、調子に乗って、さらにもう1台SDE-1000を入手し、フットペダルも増設しました。
ということで、現在、うちのSOS・ヘリコプターサウンドのシステムですが、2台のSDE-1000とBOSSのフットペダルFS-6とFS-5Uで構成されています。
見た目は大掛かりな、このシステムですが、ケーブル類も含めても1万円でおつりが出るかなり安上がりな予算で仕上がっています。
前々回のWORKING MANですが、愛用のギターアンプZenTeraのアナログのステレオラインアウトのL、Rそれぞれに1台づつSDE-1000に接続して、SDEの出力をオーディオインターフェイスに送って録音しました。
せっかく苦労して作ったシステムなので、またSOSやヘリコプターサウンドをフューチャーした曲をやりたいと思っています。
Posted by cha-key at
◆2012年03月02日00:38
│機材公開
第40回 EVENTIDE ECLIPSE
今回は、前回のSTEVE VAIのBallerina 12/24のトピックで触れた今年最後の散財について書きたいと思います。
今年最後のトピックになるであろう区切りの第40回目はEVENTIDE ECLIPSEの紹介をします。

空間系エフェクター漁りの旅も、とうとう行き着くところまで来た感があります。
分かる人には分かると思いますが、まあ、一言でいうなら、「お前、身の程をわきまえろよ アマチュアがこんなん買ってどうすんのよ?」という完全プロスペックの一品です。
アマチュアがこんなん買ってどうすんのよ?」という完全プロスペックの一品です。
定価346,500円 新品なら市場価格250,000円以上でしょうか。
新品なら市場価格250,000円以上でしょうか。
実は今年最後の散財はコレだけにとどまらず、程度の良いストラトも一緒に入手しました。
エクリプスもストラトも破格値であり、まさに千載一遇の機会で、これは行っとかなきゃダメでしょうということで勢いでいきました。
いくらなんでも、道楽に金かけるのにも程があると思われそうですが、実はコレを下取りに出したところ、予想以上の思わぬ値がついたということもあり、思い切って決断しました。
下取り代だけではさすがに資金不足だったので、諭吉さん3人に手伝っていただき、めでたく入手しました。
値段のことは野暮なので明かしませんが、普通ではなかなかできない本当によい買い物でした。
破格値でエフェクターとストラトを手に入れることができたのも驚きでしたが、15年間使用してきて、その間、ロクに手入れもしていなかったギターがあれだけの高値で引き取ってもらえたことが一番の驚きでした。
さて、EVENTIDEというメーカーですが、昔から高品質なディレイ、リバーブやハーモナイザーと呼ばれる高品質なインテリジェンスピッチシフターを開発し続け、その製品は今も昔もプロギタリストのラックの中に組み込まれています。
ジミー・ペイジ、フランク・ザッパ、ブライアン・メイ、エディ・ヴァン・へイレン、スティーヴ・ヴァイ、エッジ、ジョン・ペトルーシ、日本でもB’zの松本氏、SUGIZO氏、GRAYのHISASHI氏等々本当に多くのトッププロが使用しています。
前回のヴァイのあの曲はピッチシフターとディレイを組み合わせた独特のエフェクトサウンドが特徴となっていますが、ヴァイ本人は1990年当時、最新鋭であったH3000というラックエフェクターを使用してレコーディングをしていたかと思います。
さて、ECLIPSEですが、そのH3000の2台分に相当するDSPエンジンを搭載している、現在、EVENTIDE製品の中核を担うマルチエフェクターです。
その音質は前述した蒼々たるメンツのギタリストが認めた音だけあり、本当にスゲーとしかいえない音が出ます。
ハーモナイザーや変態モジュレーションサウンドといったいわゆる飛び道具系もよいのですが、リバーブの自然な感じが一番驚きました。
昔からエレキギターにリバーブをかけるのはあまり好きではなかったのですが、カルチャーショックというか、ちょっとリバーブに対する認識が変わりました。
これならかけっぱなしでもいいと思える音です。
また、加工されても線が細くなることなく太い音が出てきます。
搭載エフェクトの構成ですが、YAMAHAのmagic stompと同様で、コーラス、ディレイ、リバーブ等々、自分の必要なものをチョイスし組み合わせていくタイプではなく、各エフェクトの組み合わせたアルゴリズムを選択するタイプです。
ゼロベースから積み上げて音色を煮詰めていくのではなく、プリセットプログラムの中から自分のイメージに近いものを選び、調整をして仕上げていく感じでしょうか。
おそらくH3000等も同じ仕組みだと思われます。
アルゴリズムを2つ組み合わせることができるため、かなり複雑なサウンドメイクができます。
操作性は、個人的には可もなく不可もなくといったところです。
テンキーと大きなロータリーエンコーダーで各パラメータ数値を変更します。
マニュアルを読まなくても基本的なことは触っているうちにできるようになったので、操作は分かりやすいとは思いますが、正直、コンパクトエフェクターのような明快さにはかなわないと思います。
日本語マニュアルは本当に簡素なものだし、英文マニュアルは僕の能力では理解するのに時間がかかるので詳細が知りたい時などは困ります。
hot keyと呼ばれるショートカットをプログラムごとに割り当てることができるので、よく変更をするパラメーターを割り当てることで操作性を向上させることができます。
プログラムごとのパラメーターの数は多いので、音作りは結構難しい印象を受けます。
最近のエフェクターらしく、以前所有していたt.c.electronicのG-SYSTEMと同様にソフトウェアのアップデイトをすることで内蔵プログラムを増やしたり、不具合を修正することができます。
現在、var.4で、ギターアンプをシミュレートしたプログラム、同社のコンパクトエフェクターのTIME FACTOR(ディレイ)、MOD FACTOR(モジュレーション系)のパッチプログラムが加わりました。
ギターアンプは外部ペダルを接続し踏み込んでやることで、フィードバックを擬似的に起こすことができます。
結構リアルで、これだけでも、かなり遊べます。
TIME FACTOR、MOD FACTORについては以前に半年程、所有していた時期があり、操作方法も含め、どんな音が出るか分かっているのですが、同じ音がポンポンと出てくるので思わず弾きながら笑ってしまいました。(同じメーカーが作っているのだから当然といえば当然ですが)
実際の音に関しては、こちらをご覧いただければ、そのクオリティがよく分かると思います。
エフェクトのプログラム切り替えの際の音切れがあるのが玉に瑕です。
値段が値段だけに、この点については、もうちょっとどうにかならないものかと思います。
音切れの長さはデータの重さに比例しているようで、気にならない場合もあります。
ECLIPSEのみでライブパフォーマンスをし、頻繁に音色を切り替える場合は少し厳しいかもしれませんね。
トッププロのようにラックシステムに組み込んで、音色のひとつとして使用するのが正しい使い方?なのかもしれません。
まあ、自分としては、今現在はライブをやる予定もなく、専ら宅録専門なので音切れは全くもってノープロブレムです。
入出力については、さすがプロ仕様なだけありアナログ以外にデジタルもS/P DIFのコアキシャル、オプティカル、ADAT、AES/EBUを完備しています。
ちなみにウチの環境では、接続方法的に正しいかどうかは分かりませんが、ギターアンプ(Hughes & Kettner ZenTera)からECLIPSEをコアキシャルで、ECLIPSEからオーディオインターフェース(MOTU Traveler)をオプティカルで、それぞれデジタル接続しています。
そもそもデジタルアウトができるコンボギターアンプなんてあまりないと思うので、こんな接続方法をしている人はあまりいないでしょうね。
非常に気持ちいい音が出てくるので、接続方法としては特に間違っていないのかなと思います。
さあ、これから、しばらくお付き合いすることになりそうなので、はやく手なずけなければ。
今年最後のトピックになるであろう区切りの第40回目はEVENTIDE ECLIPSEの紹介をします。
空間系エフェクター漁りの旅も、とうとう行き着くところまで来た感があります。
分かる人には分かると思いますが、まあ、一言でいうなら、「お前、身の程をわきまえろよ
 アマチュアがこんなん買ってどうすんのよ?」という完全プロスペックの一品です。
アマチュアがこんなん買ってどうすんのよ?」という完全プロスペックの一品です。定価346,500円
 新品なら市場価格250,000円以上でしょうか。
新品なら市場価格250,000円以上でしょうか。実は今年最後の散財はコレだけにとどまらず、程度の良いストラトも一緒に入手しました。

エクリプスもストラトも破格値であり、まさに千載一遇の機会で、これは行っとかなきゃダメでしょうということで勢いでいきました。
いくらなんでも、道楽に金かけるのにも程があると思われそうですが、実はコレを下取りに出したところ、予想以上の思わぬ値がついたということもあり、思い切って決断しました。
下取り代だけではさすがに資金不足だったので、諭吉さん3人に手伝っていただき、めでたく入手しました。
値段のことは野暮なので明かしませんが、普通ではなかなかできない本当によい買い物でした。
破格値でエフェクターとストラトを手に入れることができたのも驚きでしたが、15年間使用してきて、その間、ロクに手入れもしていなかったギターがあれだけの高値で引き取ってもらえたことが一番の驚きでした。

さて、EVENTIDEというメーカーですが、昔から高品質なディレイ、リバーブやハーモナイザーと呼ばれる高品質なインテリジェンスピッチシフターを開発し続け、その製品は今も昔もプロギタリストのラックの中に組み込まれています。
ジミー・ペイジ、フランク・ザッパ、ブライアン・メイ、エディ・ヴァン・へイレン、スティーヴ・ヴァイ、エッジ、ジョン・ペトルーシ、日本でもB’zの松本氏、SUGIZO氏、GRAYのHISASHI氏等々本当に多くのトッププロが使用しています。
前回のヴァイのあの曲はピッチシフターとディレイを組み合わせた独特のエフェクトサウンドが特徴となっていますが、ヴァイ本人は1990年当時、最新鋭であったH3000というラックエフェクターを使用してレコーディングをしていたかと思います。
さて、ECLIPSEですが、そのH3000の2台分に相当するDSPエンジンを搭載している、現在、EVENTIDE製品の中核を担うマルチエフェクターです。
その音質は前述した蒼々たるメンツのギタリストが認めた音だけあり、本当にスゲーとしかいえない音が出ます。
ハーモナイザーや変態モジュレーションサウンドといったいわゆる飛び道具系もよいのですが、リバーブの自然な感じが一番驚きました。
昔からエレキギターにリバーブをかけるのはあまり好きではなかったのですが、カルチャーショックというか、ちょっとリバーブに対する認識が変わりました。
これならかけっぱなしでもいいと思える音です。
また、加工されても線が細くなることなく太い音が出てきます。
搭載エフェクトの構成ですが、YAMAHAのmagic stompと同様で、コーラス、ディレイ、リバーブ等々、自分の必要なものをチョイスし組み合わせていくタイプではなく、各エフェクトの組み合わせたアルゴリズムを選択するタイプです。
ゼロベースから積み上げて音色を煮詰めていくのではなく、プリセットプログラムの中から自分のイメージに近いものを選び、調整をして仕上げていく感じでしょうか。
おそらくH3000等も同じ仕組みだと思われます。
アルゴリズムを2つ組み合わせることができるため、かなり複雑なサウンドメイクができます。
操作性は、個人的には可もなく不可もなくといったところです。
テンキーと大きなロータリーエンコーダーで各パラメータ数値を変更します。
マニュアルを読まなくても基本的なことは触っているうちにできるようになったので、操作は分かりやすいとは思いますが、正直、コンパクトエフェクターのような明快さにはかなわないと思います。
日本語マニュアルは本当に簡素なものだし、英文マニュアルは僕の能力では理解するのに時間がかかるので詳細が知りたい時などは困ります。
hot keyと呼ばれるショートカットをプログラムごとに割り当てることができるので、よく変更をするパラメーターを割り当てることで操作性を向上させることができます。
プログラムごとのパラメーターの数は多いので、音作りは結構難しい印象を受けます。
最近のエフェクターらしく、以前所有していたt.c.electronicのG-SYSTEMと同様にソフトウェアのアップデイトをすることで内蔵プログラムを増やしたり、不具合を修正することができます。
現在、var.4で、ギターアンプをシミュレートしたプログラム、同社のコンパクトエフェクターのTIME FACTOR(ディレイ)、MOD FACTOR(モジュレーション系)のパッチプログラムが加わりました。
ギターアンプは外部ペダルを接続し踏み込んでやることで、フィードバックを擬似的に起こすことができます。
結構リアルで、これだけでも、かなり遊べます。
TIME FACTOR、MOD FACTORについては以前に半年程、所有していた時期があり、操作方法も含め、どんな音が出るか分かっているのですが、同じ音がポンポンと出てくるので思わず弾きながら笑ってしまいました。(同じメーカーが作っているのだから当然といえば当然ですが)
実際の音に関しては、こちらをご覧いただければ、そのクオリティがよく分かると思います。
エフェクトのプログラム切り替えの際の音切れがあるのが玉に瑕です。
値段が値段だけに、この点については、もうちょっとどうにかならないものかと思います。
音切れの長さはデータの重さに比例しているようで、気にならない場合もあります。
ECLIPSEのみでライブパフォーマンスをし、頻繁に音色を切り替える場合は少し厳しいかもしれませんね。
トッププロのようにラックシステムに組み込んで、音色のひとつとして使用するのが正しい使い方?なのかもしれません。
まあ、自分としては、今現在はライブをやる予定もなく、専ら宅録専門なので音切れは全くもってノープロブレムです。
入出力については、さすがプロ仕様なだけありアナログ以外にデジタルもS/P DIFのコアキシャル、オプティカル、ADAT、AES/EBUを完備しています。
ちなみにウチの環境では、接続方法的に正しいかどうかは分かりませんが、ギターアンプ(Hughes & Kettner ZenTera)からECLIPSEをコアキシャルで、ECLIPSEからオーディオインターフェース(MOTU Traveler)をオプティカルで、それぞれデジタル接続しています。
そもそもデジタルアウトができるコンボギターアンプなんてあまりないと思うので、こんな接続方法をしている人はあまりいないでしょうね。
非常に気持ちいい音が出てくるので、接続方法としては特に間違っていないのかなと思います。
さあ、これから、しばらくお付き合いすることになりそうなので、はやく手なずけなければ。
Posted by cha-key at
◆2011年12月15日00:23
│機材公開
第38回 Rickenbacker 4001s
前の抱きしめたいのトピックの使用機材のところで触れましたが、今回は現在、使用しているベースギターについて紹介をしたいと思います。
Rickenbacker 4001S
かれこれ10年程前に入手しました僕が所有する唯一のベースです。
わかる人にはわかるのですが、あの人が使っていたベースです。別にアーティストモデルとかシグネイチャーモデルとかではないんですが、一般的に4001Sといえばこの人というイメージでしょう。
かのポールマッカートニーがビートルズ後期からウィングス時代にメインで使用していたベースです。

昔、ビートルズのコピーバンドをやっていた時期がありました。
しかしながらベーシストがおらず、メンバー間で交代しながらベースを弾いていたのですが、いろいろな事情があり、結局、最終的には僕がベースをやることになりました。
とはいっても、僕自身は自分はギター弾きという思いがあり、ベースを弾くにしてもイヤイヤ感が強かったため、それを払拭し、後戻りができないよう退路を断つために大枚をはたいてこのベースを入手しました。
ビートルズをやるならホフナーのヴァイオリンベースなのでは?という意見もあるでしょうが、さすがにアレだと他のジャンルの音楽をやろうとすると厳しいかなと思いリッケンを選びました。
ハードロックとかにも使えそうでしたし。(ディープパープル等のイメージもありました)
まあ、今から思えば、他の音楽のことまで考えるならば、フェンダーのジャズベとかミュージックマンのスティングレイあたりを買っておけば、一番使い回しがきいたのではと思いますが...。
でも、ベースって弾いてみると面白いんですよね。
それとビートルズでベースやるってことは、ベースを弾きながら歌うことになるのですが、これが曲によってはかなり難しく、随分と練習をしました。
そういった経験ができたっていう意味ではベースを担当したことは無駄にはなっていないと思います。

まあ、そんな理由で手に入れたベースなのでルックス最優先で、音なんて二の次、アンプとエフェクトでどうにかするさ!という感じで購入しました。
独特ではありますが、このベース、本当にカッコいいシェイプをしています。
特にヘッドの部分なんか最高です。
音の方も個性的なのですが、リアピックアップはゴリゴリ、ブリブリのトレブルが効いているサウンドが特徴でしょうか。
トレブルが効いているので音の輪郭がはっきりしてフレーズが目立ちます。
フロントは、リアと比較して、まろやかでやわらかい音が出ます。
ビートルズをやるときは、主にフロントを使っていました。ハードな曲ではリアも使っていましたが...。
このブログにアップした曲ではスピッツのロビンソンとミスチルの抱きしめたいで使用していますが、2曲ともフロントで弾いています。(だったと思います。)
その他、数曲アップしている肝心のビートルズの曲のベースが打ち込みになっているところが何とも(笑)。
操作性はピックアップカバーが邪魔だし、ロングスケールだし、指弾きもスラップもやりにくい。
(もっとも専らピック弾きで、指弾きもスラップもろくにできないのですが)
はっきり言って、弾きやすいベースではないと思います。
弾き手が合わせる。それくらいの気持ちがなければこのベースは弾けないのかもしれませんね。
最近、人前で弾かなくなったので、以前と比べると使用頻度が極端に落ちていますが、何と言っても我が家の唯一のベースなので、まだまだ活躍してもらうつもりです。
Rickenbacker 4001S
かれこれ10年程前に入手しました僕が所有する唯一のベースです。
わかる人にはわかるのですが、あの人が使っていたベースです。別にアーティストモデルとかシグネイチャーモデルとかではないんですが、一般的に4001Sといえばこの人というイメージでしょう。
かのポールマッカートニーがビートルズ後期からウィングス時代にメインで使用していたベースです。

昔、ビートルズのコピーバンドをやっていた時期がありました。
しかしながらベーシストがおらず、メンバー間で交代しながらベースを弾いていたのですが、いろいろな事情があり、結局、最終的には僕がベースをやることになりました。
とはいっても、僕自身は自分はギター弾きという思いがあり、ベースを弾くにしてもイヤイヤ感が強かったため、それを払拭し、後戻りができないよう退路を断つために大枚をはたいてこのベースを入手しました。
ビートルズをやるならホフナーのヴァイオリンベースなのでは?という意見もあるでしょうが、さすがにアレだと他のジャンルの音楽をやろうとすると厳しいかなと思いリッケンを選びました。
ハードロックとかにも使えそうでしたし。(ディープパープル等のイメージもありました)
まあ、今から思えば、他の音楽のことまで考えるならば、フェンダーのジャズベとかミュージックマンのスティングレイあたりを買っておけば、一番使い回しがきいたのではと思いますが...。
でも、ベースって弾いてみると面白いんですよね。
それとビートルズでベースやるってことは、ベースを弾きながら歌うことになるのですが、これが曲によってはかなり難しく、随分と練習をしました。
そういった経験ができたっていう意味ではベースを担当したことは無駄にはなっていないと思います。
まあ、そんな理由で手に入れたベースなのでルックス最優先で、音なんて二の次、アンプとエフェクトでどうにかするさ!という感じで購入しました。
独特ではありますが、このベース、本当にカッコいいシェイプをしています。
特にヘッドの部分なんか最高です。
音の方も個性的なのですが、リアピックアップはゴリゴリ、ブリブリのトレブルが効いているサウンドが特徴でしょうか。
トレブルが効いているので音の輪郭がはっきりしてフレーズが目立ちます。
フロントは、リアと比較して、まろやかでやわらかい音が出ます。
ビートルズをやるときは、主にフロントを使っていました。ハードな曲ではリアも使っていましたが...。
このブログにアップした曲ではスピッツのロビンソンとミスチルの抱きしめたいで使用していますが、2曲ともフロントで弾いています。(だったと思います。)
その他、数曲アップしている肝心のビートルズの曲のベースが打ち込みになっているところが何とも(笑)。
操作性はピックアップカバーが邪魔だし、ロングスケールだし、指弾きもスラップもやりにくい。
(もっとも専らピック弾きで、指弾きもスラップもろくにできないのですが)
はっきり言って、弾きやすいベースではないと思います。
弾き手が合わせる。それくらいの気持ちがなければこのベースは弾けないのかもしれませんね。
最近、人前で弾かなくなったので、以前と比べると使用頻度が極端に落ちていますが、何と言っても我が家の唯一のベースなので、まだまだ活躍してもらうつもりです。
Posted by cha-key at
◆2011年11月03日22:39
│機材公開
第33回 ZEMAITIS S24 MT CUSTOM
あっ!という間に、お盆休みも終了し、また慌ただしい日常が始まります。
今年のお盆休みはパタパタしていて、休んだという感覚があまりありません。
さて、機材紹介ということで、今年の春先に手に入れたギターを紹介します。
ギターを手にするようになってから随分と長い時間が過ぎました。
やってる年数の割には、決して上手くはないし、ここ数年は人前で弾くことも、ほとんどなくなったけれども、多分、ジジイになるまで弾き続けると思います。
ならば、ここらで、一丁、一生モンのギターを手に入れてもいいのではないかと思い、思い切って買ってしまったのがコレです。

ZEMAITIS S24 MT CUSTOM (ゼマイティス メタルフロント カスタム)
新品を買うような財力はないので、程度の良い中古を探して入手しました。
中古でも30万円弱でした。
一生モンにしては値段的にケチってないかい?とツッコミが入るかもしれませんが、それでも今まで買った楽器の中で一番高価なものです。
いわゆる飲む打つ買うという習慣はほとんどないですし、同じ趣味でも車とかに比べたら、まあ、これくらいの贅沢はかわいいらしいものでしょう。と自分に言い聞かせてみる。
購入の理由として、東日本大震災もきっかけの一つになりました。
人の命の儚さとか、あの世までは金を持っていくことはできないとか。
冗談は抜きにして、これまで人生の半分くらいを生きてきて、縁起でもない話ですが、これから先、あとどれだけ生きられるのかってことを考えた時、欲しいものを買える時に買って、楽しめることができるのならば、自己満足といえど、それはそれで幸せなのではと強く思います。
シリアスな話になりましたが、そんなわけで、とにかく一生モンの買い物をしてしまいました。
さて、あらためて、このZEMAITIS S24MT CUSTOMについて紹介しますが、その前にまず、ゼマイティスというギターメーカーについて簡単に説明します。
フェンダーやギブソンのような超有名メーカーと比べると、それほど有名なメーカーではありませんが、そのギターから発せられる圧倒的な存在感からプロアマ問わず多くのファンがいます。
もともとはトニー・ゼマイティスという家具職人が若い頃にギターを買うお金がなかったので、自分でギターを作ったのがゼマイティスの始まりといわれています。
その後、改良を重ね70年代からエリック・クラプトンやビートルズのジョージ・ハリスン、ローリングストーンズのロン・ウッドといったスーパースターが使用するようになり、それ以来、ゼマイティスはギタリストにとって憧れの的になりました。
日本で有名になったのは、布袋さんがGUITARHYTHM Ⅲで使用してからでしょうね。
ちょうど、その頃から、いわゆるコピーモデルというヤツが世の中に出回り始めます。
コピーモデルといっても、ピンからキリまであるわけですが、有名どころとしてはチューンとかゼファー、そしてグレコが挙げられます。
コピーモデルでも10万とか20万とかするわけで、簡単に買うというわけにはいきませんが、トニー・ゼマイティス本人が作成したオリジナルモデルは、現在では、普通に500万円とか1,000万円とかするので、それに比べれば安いものです。
トニー・ゼマイティスは2000年代に入って高齢のため現役を引退しました。
しかし、彼の跡を継ぐものはおらず、このままではゼマイティスのギタークラフトの技術の継承が途絶えてしまう。
そんな中、完成度の高いゼマイティスのコピーモデルを作成した実績のあるグレコの親会社である神田商会が、トニー氏に対してゼマイティスブランドを譲って欲しいと打診し、交渉を開始したようです。
交渉の途中で残念ながらトニー氏は突然他界してしまうのですが、その後も遺族と交渉を続け、神田商会が正式にゼマイティスの名を受け継ぐことになったようです。
トニー氏が作ったオリジナルモデル以外は全てコピーモデルだと言ってしまえばそれまでです。
そういった意味では現行の神田商会のものもコピーモデルなのでしょうが、本家から製造工程を教わり、ゼマイティスの彫金を担っていたダニー・オブライエン等のスタッフの監修のもと、採寸等もオリジナルを再現し、ゼマイティスの名を堂々と名乗ることができることを考えれば、本家が唯一認めたコピーモデルといえるのではないでしょうか。
ゼマイティスのモデルには、大きく分けてボディトップ全面に貝をあしらったパールフロント、ボディトップにのメタルプレートを貼り付けたメタルフロント、トップ材にインレイをあしらったスーペリア、ボディトップ面の中心に円形のメタルプレートを貼り付けたディスクフロント等が挙げられます。
個人的にはゼマイティスといえばメタルフロントというイメージがあり、いつか買う日が来るならばメタルフロントを買ってやると決めていました。

で、念願かなって入手したのが、この新生ゼマイティスのS24MT CUSTOMなのですが、実は既に生産終了になっているモデルです。
メタルフロントのラインナップの中では彫金の度合いも少なく、デザイン的にかなりシンプルなモデルになっています。
最近のメタルフロントはバリバリに彫金を施したド派手なモデルが多く、それはそれでゴージャスでいいのですが、個人的にはゴチャゴチャし過ぎている感じがします。
S24MT CUSTOMくらいの派手さがちょうどいい感じです。彫金が少ない分?値段も安いし。
実際に手にしてみると、重厚そうな見た目とは違い、意外と軽いのには驚きます。
ボディ形状が似ているのでギブソンのレスポールとよく比較されるようですが、ネックはレスポールより薄いといわれています。
手元にレスポールがないので何ともいえませんが、薄いネックの部類に入る手持ちのヤマハのパシフィカと比べて、それほど違和感がないということは、それなりに薄いということになると思います。
サウンド的にはメタルプレートによりノイズが軽減されているとか、ジュラルミン削りだしのブリッジ、ハードテールで音のサスティーンが稼げるとかいわれているんですが、ノイズとかサスティーンなんてアンプのセッティング次第で変わるので僕の口からは何ともいえません。
まあ、サスティーンについては、フロイドローズタイプユニットを採用しているパシフィカと比較すれば当然ゼマイティスの方が伸びますが...。
ピックアップはディマジオ製のゼマティス専用のピックアップが搭載されています。
パシフィカにもディマジオの専用のものが搭載されていますが、パシフィカのものと比較して出力は弱いかなと感じます。
といっても、決してパワー不足というわけではなく、コードを一発鳴らした時の音の分離もイイ感じです。
パシフィカのパワーがありすぎるのかもしれませんね。
メタリックな外観から金属的な音をイメージされるかもしれませんが、実際の出音は意外と柔らかい音が出ます。
ごめんなさい。正直、音に関しては基本的にアンプとエフェクターで作るものと考えているため、細かいピックアップの違いにはそれほどこだわりません。
さすがにシングルコイルとハムバッカーの違いくらいは気にしますが...。
申し訳ございませんが、手持ちのギターだけでは比較対象が少なすぎて十分な検証ができず、これくらいの記事しか書けません。
このブログで公開している曲ではBOØWYのハイウェイに乗る前に、MORAL、BELIEVEでゼマイティスを使用しています。
しかし、これらの音を聞いても、これがゼマイティスの音かといわれると、そう言い切れるものでもなく、前述のとおり、アンプのセッティングによるところが非常に大きいと思います。
ちなみに、アンプはHughes&Kettner(ヒューズアンドケトナー)のZenTera(ゼンテラ)を使用しており、RolandのJC-120のモデリングを選択しています。
ある意味、ゼマイティスは鑑賞品ともいえるようなギターですが、楽器である以上、弾いてナンボのものだと思います。この先、遠慮なく弾き込んでいきたいギターです。
今年のお盆休みはパタパタしていて、休んだという感覚があまりありません。
さて、機材紹介ということで、今年の春先に手に入れたギターを紹介します。
ギターを手にするようになってから随分と長い時間が過ぎました。
やってる年数の割には、決して上手くはないし、ここ数年は人前で弾くことも、ほとんどなくなったけれども、多分、ジジイになるまで弾き続けると思います。
ならば、ここらで、一丁、一生モンのギターを手に入れてもいいのではないかと思い、思い切って買ってしまったのがコレです。
ZEMAITIS S24 MT CUSTOM (ゼマイティス メタルフロント カスタム)
新品を買うような財力はないので、程度の良い中古を探して入手しました。
中古でも30万円弱でした。
一生モンにしては値段的にケチってないかい?とツッコミが入るかもしれませんが、それでも今まで買った楽器の中で一番高価なものです。
いわゆる飲む打つ買うという習慣はほとんどないですし、同じ趣味でも車とかに比べたら、まあ、これくらいの贅沢はかわいいらしいものでしょう。と自分に言い聞かせてみる。
購入の理由として、東日本大震災もきっかけの一つになりました。
人の命の儚さとか、あの世までは金を持っていくことはできないとか。
冗談は抜きにして、これまで人生の半分くらいを生きてきて、縁起でもない話ですが、これから先、あとどれだけ生きられるのかってことを考えた時、欲しいものを買える時に買って、楽しめることができるのならば、自己満足といえど、それはそれで幸せなのではと強く思います。
シリアスな話になりましたが、そんなわけで、とにかく一生モンの買い物をしてしまいました。
さて、あらためて、このZEMAITIS S24MT CUSTOMについて紹介しますが、その前にまず、ゼマイティスというギターメーカーについて簡単に説明します。
フェンダーやギブソンのような超有名メーカーと比べると、それほど有名なメーカーではありませんが、そのギターから発せられる圧倒的な存在感からプロアマ問わず多くのファンがいます。
もともとはトニー・ゼマイティスという家具職人が若い頃にギターを買うお金がなかったので、自分でギターを作ったのがゼマイティスの始まりといわれています。
その後、改良を重ね70年代からエリック・クラプトンやビートルズのジョージ・ハリスン、ローリングストーンズのロン・ウッドといったスーパースターが使用するようになり、それ以来、ゼマイティスはギタリストにとって憧れの的になりました。
日本で有名になったのは、布袋さんがGUITARHYTHM Ⅲで使用してからでしょうね。
ちょうど、その頃から、いわゆるコピーモデルというヤツが世の中に出回り始めます。
コピーモデルといっても、ピンからキリまであるわけですが、有名どころとしてはチューンとかゼファー、そしてグレコが挙げられます。
コピーモデルでも10万とか20万とかするわけで、簡単に買うというわけにはいきませんが、トニー・ゼマイティス本人が作成したオリジナルモデルは、現在では、普通に500万円とか1,000万円とかするので、それに比べれば安いものです。
トニー・ゼマイティスは2000年代に入って高齢のため現役を引退しました。
しかし、彼の跡を継ぐものはおらず、このままではゼマイティスのギタークラフトの技術の継承が途絶えてしまう。
そんな中、完成度の高いゼマイティスのコピーモデルを作成した実績のあるグレコの親会社である神田商会が、トニー氏に対してゼマイティスブランドを譲って欲しいと打診し、交渉を開始したようです。
交渉の途中で残念ながらトニー氏は突然他界してしまうのですが、その後も遺族と交渉を続け、神田商会が正式にゼマイティスの名を受け継ぐことになったようです。
トニー氏が作ったオリジナルモデル以外は全てコピーモデルだと言ってしまえばそれまでです。
そういった意味では現行の神田商会のものもコピーモデルなのでしょうが、本家から製造工程を教わり、ゼマイティスの彫金を担っていたダニー・オブライエン等のスタッフの監修のもと、採寸等もオリジナルを再現し、ゼマイティスの名を堂々と名乗ることができることを考えれば、本家が唯一認めたコピーモデルといえるのではないでしょうか。
ゼマイティスのモデルには、大きく分けてボディトップ全面に貝をあしらったパールフロント、ボディトップにのメタルプレートを貼り付けたメタルフロント、トップ材にインレイをあしらったスーペリア、ボディトップ面の中心に円形のメタルプレートを貼り付けたディスクフロント等が挙げられます。
個人的にはゼマイティスといえばメタルフロントというイメージがあり、いつか買う日が来るならばメタルフロントを買ってやると決めていました。
で、念願かなって入手したのが、この新生ゼマイティスのS24MT CUSTOMなのですが、実は既に生産終了になっているモデルです。
メタルフロントのラインナップの中では彫金の度合いも少なく、デザイン的にかなりシンプルなモデルになっています。
最近のメタルフロントはバリバリに彫金を施したド派手なモデルが多く、それはそれでゴージャスでいいのですが、個人的にはゴチャゴチャし過ぎている感じがします。
S24MT CUSTOMくらいの派手さがちょうどいい感じです。彫金が少ない分?値段も安いし。
実際に手にしてみると、重厚そうな見た目とは違い、意外と軽いのには驚きます。
ボディ形状が似ているのでギブソンのレスポールとよく比較されるようですが、ネックはレスポールより薄いといわれています。
手元にレスポールがないので何ともいえませんが、薄いネックの部類に入る手持ちのヤマハのパシフィカと比べて、それほど違和感がないということは、それなりに薄いということになると思います。
サウンド的にはメタルプレートによりノイズが軽減されているとか、ジュラルミン削りだしのブリッジ、ハードテールで音のサスティーンが稼げるとかいわれているんですが、ノイズとかサスティーンなんてアンプのセッティング次第で変わるので僕の口からは何ともいえません。
まあ、サスティーンについては、フロイドローズタイプユニットを採用しているパシフィカと比較すれば当然ゼマイティスの方が伸びますが...。
ピックアップはディマジオ製のゼマティス専用のピックアップが搭載されています。
パシフィカにもディマジオの専用のものが搭載されていますが、パシフィカのものと比較して出力は弱いかなと感じます。
といっても、決してパワー不足というわけではなく、コードを一発鳴らした時の音の分離もイイ感じです。
パシフィカのパワーがありすぎるのかもしれませんね。
メタリックな外観から金属的な音をイメージされるかもしれませんが、実際の出音は意外と柔らかい音が出ます。
ごめんなさい。正直、音に関しては基本的にアンプとエフェクターで作るものと考えているため、細かいピックアップの違いにはそれほどこだわりません。
さすがにシングルコイルとハムバッカーの違いくらいは気にしますが...。
申し訳ございませんが、手持ちのギターだけでは比較対象が少なすぎて十分な検証ができず、これくらいの記事しか書けません。
このブログで公開している曲ではBOØWYのハイウェイに乗る前に、MORAL、BELIEVEでゼマイティスを使用しています。
しかし、これらの音を聞いても、これがゼマイティスの音かといわれると、そう言い切れるものでもなく、前述のとおり、アンプのセッティングによるところが非常に大きいと思います。
ちなみに、アンプはHughes&Kettner(ヒューズアンドケトナー)のZenTera(ゼンテラ)を使用しており、RolandのJC-120のモデリングを選択しています。
ある意味、ゼマイティスは鑑賞品ともいえるようなギターですが、楽器である以上、弾いてナンボのものだと思います。この先、遠慮なく弾き込んでいきたいギターです。
Posted by cha-key at
◆2011年08月17日18:03
│機材公開